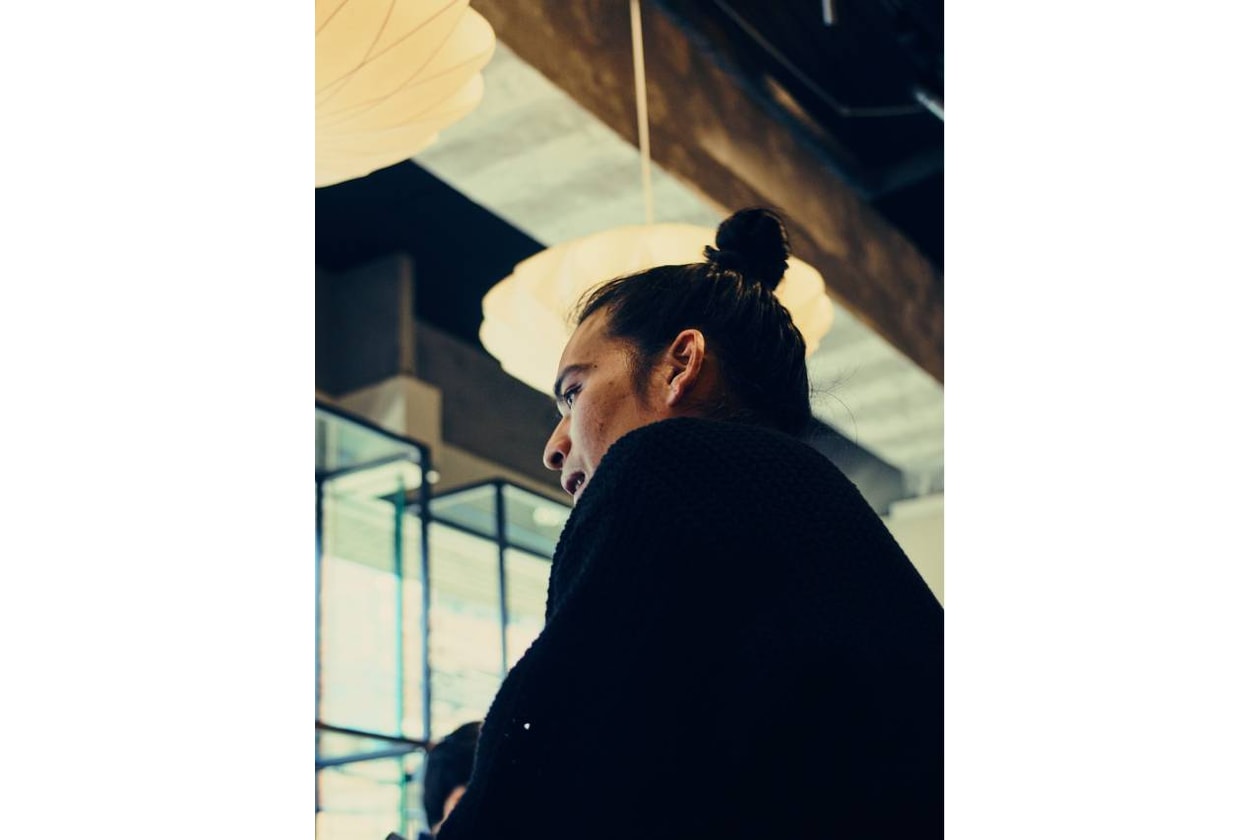Rewrite
ドメスティックブランドが成長し、国内外へと広がっていく過程において、PRの役割は大きく変化している。単にメディア露出を増やすだけの“表層的なPR”では、ブランドの価値や思想が正しく伝わりにくくなった今、求められているのは、より深いレイヤーでブランドと向き合い、共に時間を重ねていく存在だ。
PRエージェンシー「4K(シック)」は、そうした変化を体現してきた存在のひとつだろう。〈SUGARHILL(シュガーヒル)〉や〈DAIRIKU(ダイリク)〉といった気鋭のドメスティックブランドがまだ駆け出しだった頃から関わり、契約前の展示会を手伝い、PRにとどまらずセールス面まで含めてブランドと並走してきた。そこにあるのは、「ブランドと一緒になって、日本のカルチャーシーンの継承と更新を続けていく」というスタンスのもと、外部パートナーという距離を超えて、チームの一員として関係性を積み上げていく姿勢だ。デザイナーは安心して表現とものづくりに集中し、その積み重ねが、ブランドの輪郭と信頼を少しずつ強固なものにしてきた。
本企画では、4Kディレクターの河村充倫が聞き手を務め、〈SUGARHILL〉デザイナーの林陸也、〈DAIRIKU〉デザイナーの岡本大陸とともに、これまでの歩みを振り返る。初のランウェイショーで得た手応えと反省、節目に再びランウェイへと向かった理由、映像制作や海外展示会を通じて得た視点の変化、そして次世代へと視線が移り始めたいまの実感まで。ブランドとエージェントは、どこまで同じ景色を見られるのか。
河村充倫(以下、K):大陸と陸也が2人そろって初ランウェイ、しかも同日開催(3月19日)となった2022年秋冬コレクションの東京ファッションウィークは、僕にとっても思い出深い出来事でした。2人は、あの時を振り返ってどう?
林陸也(以下、H):2022年秋冬はSUGARHILLにとって初めてのランウェイでしたが、正直「通過点の一つ」という感覚が一番強かったです。それまでは服そのものの強度で勝負してきたつもりでしたし、SUGARHILLはランウェイ向きではないと思っていた部分もあって、ショーをすること自体に迷いもありました。でも結果的に、ランウェイという「時間と空間を含めた表現」に挑戦したことは大きな糧になりました。難儀した部分や反省点も多かったけど、それも含めてその時点の自分たちが出せる正直な表現だったと思います。経験したことで、次に何を更新すべきかが明確になった。今のSUGARHILLにつながる重要な起点だった感覚があります。
K:そっか。陸也はショーが決まったときから冷静というか、演出家をどうするか、会場のディレクション含めて方針が明確だった印象がある。(ファッションショーの演出を行う)bonの蔭山くんや、万城男さんも陸也が決めてきて、スルっと進んだ気がする。逆に、大陸はKuRoKoの演出家・齊藤くんにお願いするところから始まった。当時は、他のブランドと同じ会場だから、どう違いを出すか、いろいろ3人で議論したよね。
岡本大陸(以下、O):僕は高校時代に過ごしたアメ村での服との出会いがテーマで、そこで出会った友達や先輩は今でも仲良くしてもらってたり、一緒に仕事したりしていて。原点が詰まった思い出深いランウェイでした。演出面では、フェリーニの映画『8 1/2』のラストシーンが大好きで、その空気感に感化されて。アメ村で出会った服や人々をイメージしたスタイリングで、そのセットを再現して歩き回る演出にしたくて、斎藤さんと渋谷ヒカリエでどう表現して観客に伝えるか、連日議論しました。初の単独ランウェイということもあって、ショーにかける思いは人一倍強かったですね。あと、スタイリストの渕上寛さんには感謝しかないです。
K:なるほど、不思議と来場したバイヤーやメディアの反応が、2ブランドで大きく違ってて、もちろんショーというかブランドの方向性が違うから、比較するもんでもないんだけど、DAIRIKUは、もうみんなが感動巨編の映画を観終わった後って感じで。同年代のファッション関係者や、表現者からの大陸本人に対しての「おめでとう!」の声がすごかった。ああ、大陸って人気ものなんだなって、まわりの声援やばいなって思った。その点、SUGARHILLのお客さんは、「美術館でいい作家の展示みられました!」みたいなコメントで、踊ってばかりの国の生演奏を会場の中心に配置した、シンプルな演出だったけど、ショーに引き込まれた的な反響だった。「これで、初めてって、クオリティすごくない?」ってみんな言ってた。
H:改めて嬉しいですね。会場でしか生まれない没入感や臨場感をどうつくるかは意識していました。派手さよりも、SUGARHILLの温度感や服が生まれる土壌をどう可視化するかを重視していたので。反省点も含めて、等身大の正直な表現だったと思います。
K:2026年春夏シーズンで久しぶりにランウェイショーをやったじゃない。シンプルになんで?しかも2月6日には、またランウェイショーも控えてる。「2シーズン連続でショーをやる」って、いきなり事務所に来て言い放って帰っていったよね(笑)。「よろしくっす!」みたいな感じで。
H:10周年という節目でランウェイを行うことは、記念というより「もう一度、SUGARHILLが今どこに立っているのかを確認する作業」に近いっていうか。ランウェイから距離を置いていた期間に、服作りそのものやチームとしての在り方は成熟してきた。その積み重ねを久しぶりに立体的に外へ提示した感覚です。演出全体は前回同様bonにお願いして土台を組んでもらっています。その上で、ビジュアル、キャスティング、全体構成、細部の判断まで、クリエイティブの中核はほぼ自分たちのチームで担っている。ブランドのフェーズが変わって、「任せる」だけじゃなく、「自分たちで決断する」割合が増えました。2月6日の2026年秋冬ランウェイショーは、2026年春夏で得た手応えと反省をそのままぶつけられるのが大きい。同じ空間でも意味は全く変わるはずなので、連続性の中でどれだけ更新できるかに挑戦したいです。
K:なるほど。もうすぐだね、頑張って。僕としても、また一緒にショーができるのが嬉しいし、直接事務所に「おねしゃす!」って来られると、こっちも気合が入る。来月、よろしくね。
DAIRIKUの“映画”が変えた、服作りの視点
K:区切りといえば、大陸は映画制作と上映会をやったよね。ショーとは全然勝手が違うし、大変だったでしょ?
O:もともと映画が好きで、映画をテーマに服を作ってきたので、いつか映画を作りたいってずっと思ってました。2025年春夏で挑戦して実現できた短編SF映画『AISLE』は思い出深いです。脚本もオリジナルで、セット作りからストーリーを考えるのが本当に大変でした。でも(クリエイティブユニット)MargtのArataくん、ISSAくんに協力してもらって完成できたし、主演の山﨑賢人さん、栁俊太郎さんのおかげで映像に命が宿りました。この場を借りて、改めてありがとうございます。
K:やっぱ一つの達成感というか、夢が叶った感覚はあった?
O:大変だった分、達成感は大きかったです。上映の時にお客さんの反応を待つドキドキは、ショーの緊張感と変わらない。それと、映画を作ったことで「自分は半年先、1年先のファッションを提案してる」って思い始めたというか。SF映画を作って未来に提案してる感覚に近くて、服作りの考え方が変わり始めました。
K:その思考にいきつくのが大陸らしい。挑戦を繰り返して進化していくんだな、ブランドって。
パリで突きつけられる「評価」と「宿題」
K:2人ともパリで展示会を続けてるよね。反応や手応えはどう?
H:毎回、「自分たちがどこで、どう評価されているのか」を突きつけられる場だと感じています。デザインの強さや素材への向き合い方は、確実にリアクションが良くなっている実感がありますね。一方で海外進出に関しては、価格と価値の伝え方、商品のデリバリー、ソーシャルメディア上でのコミュニケーションなど、服そのもの以外にまだ多くの課題がある。短期的な拡大を狙うより、理解される速度を大切にしながら進めている段階です。
O:パリの展示会は4回やってるんですが、僕にとってはいつも宿題を渡される場所でもあって。日本人として、日本ブランドとして、国外にも影響を与えたい気持ちはずっと変わらない。Paleduskというバンドのカイトという最高の友達の言葉なんですけど、「大切なことは日本語で伝える」っていう一言をもらって、服作りもそうだなって思った。陸也が言うように、海外セールスに関しては、課題は山積みだけど、まず自分が日本人デザイナーとして伝えたいことを明確にして、洋服作りに取り組むことが改めて大事だと感じています。
K:大陸はやっぱりロマンティック路線だね(笑)。でも嫌いじゃない。日本人として、日本ブランドとして、は確かに重要だし、ルーツの誇りにもつながる。大陸はいつも地元の大阪感があるし(笑)。パリでのショーも視野にある?
O:あります!あと路面店を作りたい。映画も次は長編に挑戦してみたい。あとは今思ったんですけど、陸也と音楽イベントとかやってみたいですね。
K:陸也は?
H:大きな夢としては、SUGARHILLが一つの「価値観」として成立することです。単に服を作るブランドではなく、どういう姿勢で物作りをしているのか、どんな時間の積み重ねを信じているのか、そこまで含めて支持される存在になりたい。規模を大きくすること自体がゴールではなく、「続いていくこと」「更新し続けられること」が重要。10年続いたからこそ、次の10年はより誠実に向き合っていきたいです。
K:出た、陸也の哲学的なやつ(笑)。もはやどっちが先輩かわかんなくなるね。二人がこうして会うのは久々だよね。ぶっちゃけ、お互い意識してたりする?
H:同業というより友達として、大陸は自分にはできないことをやっている人。発想のスピード、ものごとを前に進めるエネルギー、人を巻き込む力が本当にある。自分は立ち止まって考えすぎるタイプなので、驚かされることが多いし、純粋に尊敬してます。それぞれが得意な場所で全力を出している関係性だと思いますし、そういう同世代の存在が近くにいることにいつも刺激をもらっています。
O:腐れ縁な感じもするけどね(笑)。デビュー当初の合同展示会も一緒で、初ランウェイをするタイミングも、会場も同じで。20代の時はめっちゃ喧嘩もしました。でも陸也の服作りは本当に尊敬してます。僕には作れない、なんというか、おっとりする服を作りはるんですよ。
K:いいね。同時代を駆け抜けてる同世代のデザイナー2人。さっき言ってた音楽イベント、ぜひやってよ。それに、今は2人の挑戦を支えるだけじゃなくて、その先の世代も動き始めてる。DAIRIKUの後進としてLITTLE BEDROOM(リトルベッドルーム)というブランドもうちで育て始めていて、まだ2シーズン目。面白いのは、その次世代に対して“大陸自身”も自然と手を差し伸べていること。卸先を連れていったり、グラフィックを頼んだり、いろいろ面倒を見てくれてる。エージェントの立場からすると、先を走る彼らの背中を見て次世代が追いかけていく、その“両方の景色”を同時に見られるのは、やっぱり楽しみだし、励みになるね。
SUGARHILL
デザイナー 林陸也により2016年に設立。ニューヨーク・FIT留学時に生活していた地区名に由来するブランド名の通り、日本的な感性とアメリカーナをベースに、パンクやグランジのエッセンスを織り交ぜた独自の世界観を構築している。過去の衣服研究を起点に、素材開発や特殊な加工技法を追求。インディゴやアイアン、レザーの経年変化にフォーカスしながら、現代的なシルエットとカラーリングで再解釈する。日常的なワークウェアを題材に、音楽カルチャーからの強い影響を反映したラフさと鋭さを併せ持つコレクションを展開。卓越したファブリック使いと加工技術に定評があり、とりわけレザーやデニムアイテムにおいて高い評価を獲得している。
DAIRIKU
デザイナーの岡本大陸により2018年春夏よりスタート。毎シーズン“映画”をテーマに据え、ルーツやストーリーを感じさせるコレクションを展開している。「VANTANデザイン研究所」在学中に「Asia Fashion Collection」でグランプリを獲得し、NY FASHION WEEKにてランウェイ形式でコレクションを発表。2018年春夏シーズンより展示会形式で本格的にブランドをスタートさせた。2021年には「TOKYO FASHION AWARD 2022」を受賞。翌2022年3月の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」では、2022年秋冬コレクションをランウェイ形式で発表するなど、国内外で存在感を確立。以降も2024春夏、2024秋冬コレクションを立て続けにランウェイで発表し、物語性と現代性を併せ持つ独自のスタイルを進化させ続けている。
4K
「4K」は、東京を拠点に国内外のファッションブランドをサポートするPR/ホールセールカンパニー。メディアリレーションやデジタル施策を軸に、ブランドの世界観を的確に発信し、マーケットとの接点を構築している。2018年には〈CarService〉ディレクター・橋本奎のディレクションのもと、アートスタジオ『4N』をオープン。国内外の気鋭アーティストをキュレーションし、個展やグループエキシビションを開催するなど、カルチャーシーンとも密接にリンク。2024年にはランニング&サイクリングステーション『FO Sports Club』をオープン。『DAIKANYAMA RUN&CHILL』を定期開催し、様々なジャンルの参加者が集い、コミュニティーを広げている。ファッションとアート、カルチャーを横断する視点を武器に、現代的なPRカンパニーとしての機能と、シーンと並走してきた確かなバックグラウンドを併せ持つ存在だ。
in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing
tags from
ドメスティックブランドが成長し、国内外へと広がっていく過程において、PRの役割は大きく変化している。単にメディア露出を増やすだけの“表層的なPR”では、ブランドの価値や思想が正しく伝わりにくくなった今、求められているのは、より深いレイヤーでブランドと向き合い、共に時間を重ねていく存在だ。
PRエージェンシー「4K(シック)」は、そうした変化を体現してきた存在のひとつだろう。〈SUGARHILL(シュガーヒル)〉や〈DAIRIKU(ダイリク)〉といった気鋭のドメスティックブランドがまだ駆け出しだった頃から関わり、契約前の展示会を手伝い、PRにとどまらずセールス面まで含めてブランドと並走してきた。そこにあるのは、「ブランドと一緒になって、日本のカルチャーシーンの継承と更新を続けていく」というスタンスのもと、外部パートナーという距離を超えて、チームの一員として関係性を積み上げていく姿勢だ。デザイナーは安心して表現とものづくりに集中し、その積み重ねが、ブランドの輪郭と信頼を少しずつ強固なものにしてきた。
本企画では、4Kディレクターの河村充倫が聞き手を務め、〈SUGARHILL〉デザイナーの林陸也、〈DAIRIKU〉デザイナーの岡本大陸とともに、これまでの歩みを振り返る。初のランウェイショーで得た手応えと反省、節目に再びランウェイへと向かった理由、映像制作や海外展示会を通じて得た視点の変化、そして次世代へと視線が移り始めたいまの実感まで。ブランドとエージェントは、どこまで同じ景色を見られるのか。
河村充倫(以下、K):大陸と陸也が2人そろって初ランウェイ、しかも同日開催(3月19日)となった2022年秋冬コレクションの東京ファッションウィークは、僕にとっても思い出深い出来事でした。2人は、あの時を振り返ってどう?
林陸也(以下、H):2022年秋冬はSUGARHILLにとって初めてのランウェイでしたが、正直「通過点の一つ」という感覚が一番強かったです。それまでは服そのものの強度で勝負してきたつもりでしたし、SUGARHILLはランウェイ向きではないと思っていた部分もあって、ショーをすること自体に迷いもありました。でも結果的に、ランウェイという「時間と空間を含めた表現」に挑戦したことは大きな糧になりました。難儀した部分や反省点も多かったけど、それも含めてその時点の自分たちが出せる正直な表現だったと思います。経験したことで、次に何を更新すべきかが明確になった。今のSUGARHILLにつながる重要な起点だった感覚があります。
K:そっか。陸也はショーが決まったときから冷静というか、演出家をどうするか、会場のディレクション含めて方針が明確だった印象がある。(ファッションショーの演出を行う)bonの蔭山くんや、万城男さんも陸也が決めてきて、スルっと進んだ気がする。逆に、大陸はKuRoKoの演出家・齊藤くんにお願いするところから始まった。当時は、他のブランドと同じ会場だから、どう違いを出すか、いろいろ3人で議論したよね。
岡本大陸(以下、O):僕は高校時代に過ごしたアメ村での服との出会いがテーマで、そこで出会った友達や先輩は今でも仲良くしてもらってたり、一緒に仕事したりしていて。原点が詰まった思い出深いランウェイでした。演出面では、フェリーニの映画『8 1/2』のラストシーンが大好きで、その空気感に感化されて。アメ村で出会った服や人々をイメージしたスタイリングで、そのセットを再現して歩き回る演出にしたくて、斎藤さんと渋谷ヒカリエでどう表現して観客に伝えるか、連日議論しました。初の単独ランウェイということもあって、ショーにかける思いは人一倍強かったですね。あと、スタイリストの渕上寛さんには感謝しかないです。
K:なるほど、不思議と来場したバイヤーやメディアの反応が、2ブランドで大きく違ってて、もちろんショーというかブランドの方向性が違うから、比較するもんでもないんだけど、DAIRIKUは、もうみんなが感動巨編の映画を観終わった後って感じで。同年代のファッション関係者や、表現者からの大陸本人に対しての「おめでとう!」の声がすごかった。ああ、大陸って人気ものなんだなって、まわりの声援やばいなって思った。その点、SUGARHILLのお客さんは、「美術館でいい作家の展示みられました!」みたいなコメントで、踊ってばかりの国の生演奏を会場の中心に配置した、シンプルな演出だったけど、ショーに引き込まれた的な反響だった。「これで、初めてって、クオリティすごくない?」ってみんな言ってた。
H:改めて嬉しいですね。会場でしか生まれない没入感や臨場感をどうつくるかは意識していました。派手さよりも、SUGARHILLの温度感や服が生まれる土壌をどう可視化するかを重視していたので。反省点も含めて、等身大の正直な表現だったと思います。
K:2026年春夏シーズンで久しぶりにランウェイショーをやったじゃない。シンプルになんで?しかも2月6日には、またランウェイショーも控えてる。「2シーズン連続でショーをやる」って、いきなり事務所に来て言い放って帰っていったよね(笑)。「よろしくっす!」みたいな感じで。
H:10周年という節目でランウェイを行うことは、記念というより「もう一度、SUGARHILLが今どこに立っているのかを確認する作業」に近いっていうか。ランウェイから距離を置いていた期間に、服作りそのものやチームとしての在り方は成熟してきた。その積み重ねを久しぶりに立体的に外へ提示した感覚です。演出全体は前回同様bonにお願いして土台を組んでもらっています。その上で、ビジュアル、キャスティング、全体構成、細部の判断まで、クリエイティブの中核はほぼ自分たちのチームで担っている。ブランドのフェーズが変わって、「任せる」だけじゃなく、「自分たちで決断する」割合が増えました。2月6日の2026年秋冬ランウェイショーは、2026年春夏で得た手応えと反省をそのままぶつけられるのが大きい。同じ空間でも意味は全く変わるはずなので、連続性の中でどれだけ更新できるかに挑戦したいです。
K:なるほど。もうすぐだね、頑張って。僕としても、また一緒にショーができるのが嬉しいし、直接事務所に「おねしゃす!」って来られると、こっちも気合が入る。来月、よろしくね。
DAIRIKUの“映画”が変えた、服作りの視点
K:区切りといえば、大陸は映画制作と上映会をやったよね。ショーとは全然勝手が違うし、大変だったでしょ?
O:もともと映画が好きで、映画をテーマに服を作ってきたので、いつか映画を作りたいってずっと思ってました。2025年春夏で挑戦して実現できた短編SF映画『AISLE』は思い出深いです。脚本もオリジナルで、セット作りからストーリーを考えるのが本当に大変でした。でも(クリエイティブユニット)MargtのArataくん、ISSAくんに協力してもらって完成できたし、主演の山﨑賢人さん、栁俊太郎さんのおかげで映像に命が宿りました。この場を借りて、改めてありがとうございます。
K:やっぱ一つの達成感というか、夢が叶った感覚はあった?
O:大変だった分、達成感は大きかったです。上映の時にお客さんの反応を待つドキドキは、ショーの緊張感と変わらない。それと、映画を作ったことで「自分は半年先、1年先のファッションを提案してる」って思い始めたというか。SF映画を作って未来に提案してる感覚に近くて、服作りの考え方が変わり始めました。
K:その思考にいきつくのが大陸らしい。挑戦を繰り返して進化していくんだな、ブランドって。
パリで突きつけられる「評価」と「宿題」
K:2人ともパリで展示会を続けてるよね。反応や手応えはどう?
H:毎回、「自分たちがどこで、どう評価されているのか」を突きつけられる場だと感じています。デザインの強さや素材への向き合い方は、確実にリアクションが良くなっている実感がありますね。一方で海外進出に関しては、価格と価値の伝え方、商品のデリバリー、ソーシャルメディア上でのコミュニケーションなど、服そのもの以外にまだ多くの課題がある。短期的な拡大を狙うより、理解される速度を大切にしながら進めている段階です。
O:パリの展示会は4回やってるんですが、僕にとってはいつも宿題を渡される場所でもあって。日本人として、日本ブランドとして、国外にも影響を与えたい気持ちはずっと変わらない。Paleduskというバンドのカイトという最高の友達の言葉なんですけど、「大切なことは日本語で伝える」っていう一言をもらって、服作りもそうだなって思った。陸也が言うように、海外セールスに関しては、課題は山積みだけど、まず自分が日本人デザイナーとして伝えたいことを明確にして、洋服作りに取り組むことが改めて大事だと感じています。
K:大陸はやっぱりロマンティック路線だね(笑)。でも嫌いじゃない。日本人として、日本ブランドとして、は確かに重要だし、ルーツの誇りにもつながる。大陸はいつも地元の大阪感があるし(笑)。パリでのショーも視野にある?
O:あります!あと路面店を作りたい。映画も次は長編に挑戦してみたい。あとは今思ったんですけど、陸也と音楽イベントとかやってみたいですね。
K:陸也は?
H:大きな夢としては、SUGARHILLが一つの「価値観」として成立することです。単に服を作るブランドではなく、どういう姿勢で物作りをしているのか、どんな時間の積み重ねを信じているのか、そこまで含めて支持される存在になりたい。規模を大きくすること自体がゴールではなく、「続いていくこと」「更新し続けられること」が重要。10年続いたからこそ、次の10年はより誠実に向き合っていきたいです。
K:出た、陸也の哲学的なやつ(笑)。もはやどっちが先輩かわかんなくなるね。二人がこうして会うのは久々だよね。ぶっちゃけ、お互い意識してたりする?
H:同業というより友達として、大陸は自分にはできないことをやっている人。発想のスピード、ものごとを前に進めるエネルギー、人を巻き込む力が本当にある。自分は立ち止まって考えすぎるタイプなので、驚かされることが多いし、純粋に尊敬してます。それぞれが得意な場所で全力を出している関係性だと思いますし、そういう同世代の存在が近くにいることにいつも刺激をもらっています。
O:腐れ縁な感じもするけどね(笑)。デビュー当初の合同展示会も一緒で、初ランウェイをするタイミングも、会場も同じで。20代の時はめっちゃ喧嘩もしました。でも陸也の服作りは本当に尊敬してます。僕には作れない、なんというか、おっとりする服を作りはるんですよ。
K:いいね。同時代を駆け抜けてる同世代のデザイナー2人。さっき言ってた音楽イベント、ぜひやってよ。それに、今は2人の挑戦を支えるだけじゃなくて、その先の世代も動き始めてる。DAIRIKUの後進としてLITTLE BEDROOM(リトルベッドルーム)というブランドもうちで育て始めていて、まだ2シーズン目。面白いのは、その次世代に対して“大陸自身”も自然と手を差し伸べていること。卸先を連れていったり、グラフィックを頼んだり、いろいろ面倒を見てくれてる。エージェントの立場からすると、先を走る彼らの背中を見て次世代が追いかけていく、その“両方の景色”を同時に見られるのは、やっぱり楽しみだし、励みになるね。
SUGARHILL
デザイナー 林陸也により2016年に設立。ニューヨーク・FIT留学時に生活していた地区名に由来するブランド名の通り、日本的な感性とアメリカーナをベースに、パンクやグランジのエッセンスを織り交ぜた独自の世界観を構築している。過去の衣服研究を起点に、素材開発や特殊な加工技法を追求。インディゴやアイアン、レザーの経年変化にフォーカスしながら、現代的なシルエットとカラーリングで再解釈する。日常的なワークウェアを題材に、音楽カルチャーからの強い影響を反映したラフさと鋭さを併せ持つコレクションを展開。卓越したファブリック使いと加工技術に定評があり、とりわけレザーやデニムアイテムにおいて高い評価を獲得している。
DAIRIKU
デザイナーの岡本大陸により2018年春夏よりスタート。毎シーズン“映画”をテーマに据え、ルーツやストーリーを感じさせるコレクションを展開している。「VANTANデザイン研究所」在学中に「Asia Fashion Collection」でグランプリを獲得し、NY FASHION WEEKにてランウェイ形式でコレクションを発表。2018年春夏シーズンより展示会形式で本格的にブランドをスタートさせた。2021年には「TOKYO FASHION AWARD 2022」を受賞。翌2022年3月の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」では、2022年秋冬コレクションをランウェイ形式で発表するなど、国内外で存在感を確立。以降も2024春夏、2024秋冬コレクションを立て続けにランウェイで発表し、物語性と現代性を併せ持つ独自のスタイルを進化させ続けている。
4K
「4K」は、東京を拠点に国内外のファッションブランドをサポートするPR/ホールセールカンパニー。メディアリレーションやデジタル施策を軸に、ブランドの世界観を的確に発信し、マーケットとの接点を構築している。2018年には〈CarService〉ディレクター・橋本奎のディレクションのもと、アートスタジオ『4N』をオープン。国内外の気鋭アーティストをキュレーションし、個展やグループエキシビションを開催するなど、カルチャーシーンとも密接にリンク。2024年にはランニング&サイクリングステーション『FO Sports Club』をオープン。『DAIKANYAMA RUN&CHILL』を定期開催し、様々なジャンルの参加者が集い、コミュニティーを広げている。ファッションとアート、カルチャーを横断する視点を武器に、現代的なPRカンパニーとしての機能と、シーンと並走してきた確かなバックグラウンドを併せ持つ存在だ。
and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.