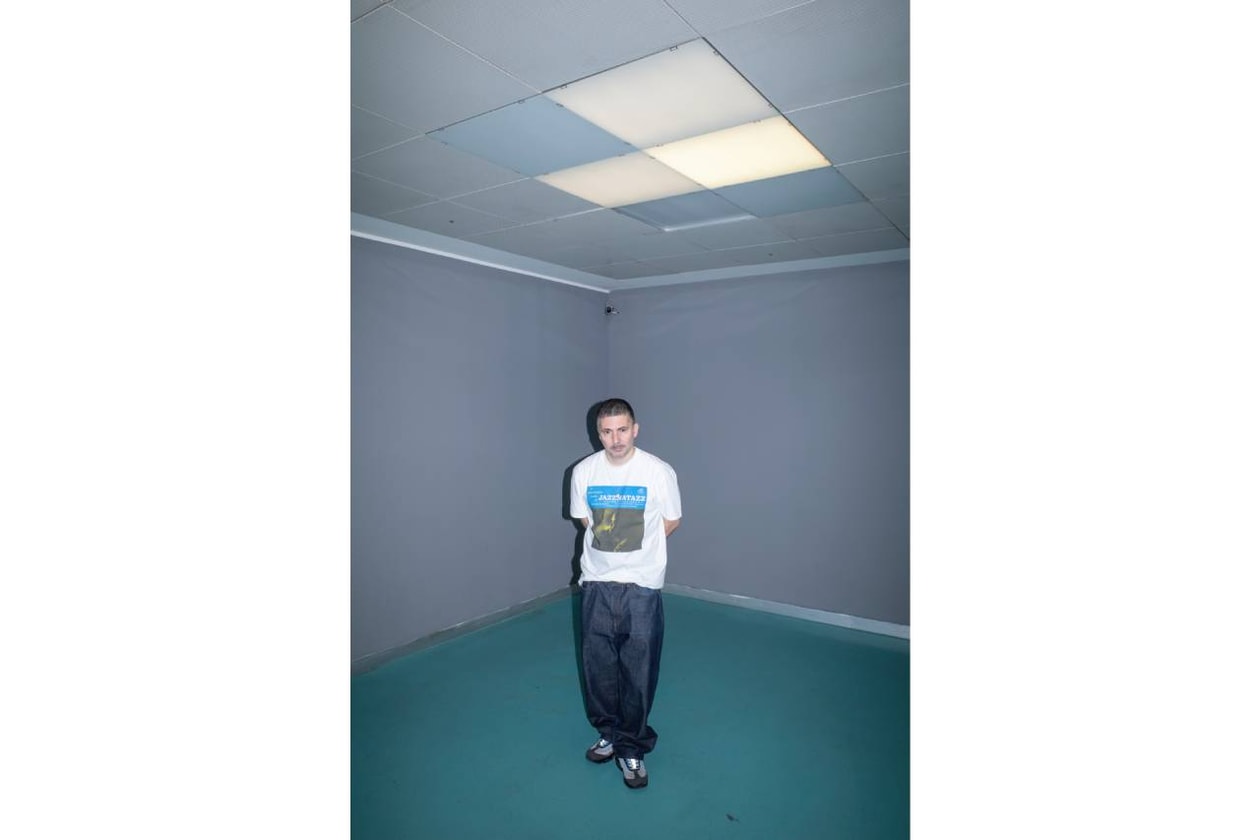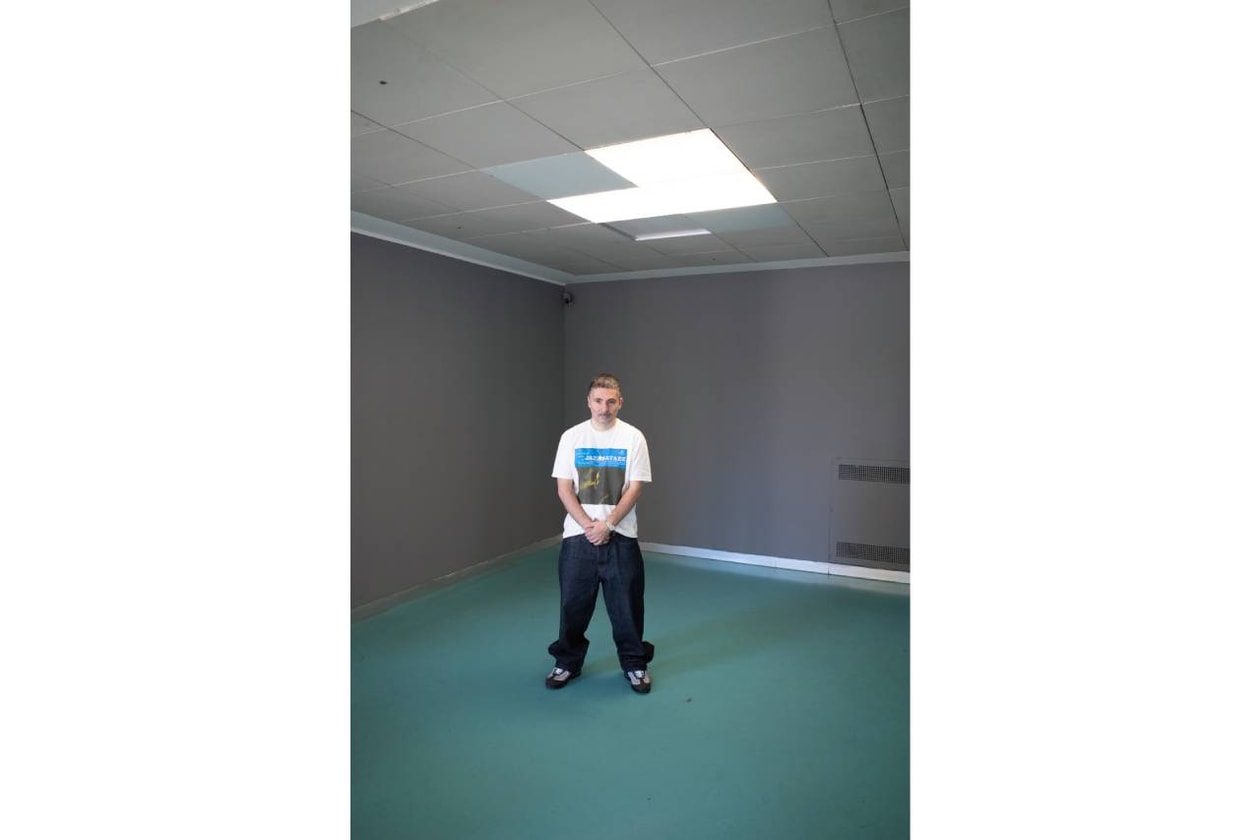Rewrite
スケートボーディングと音楽。両者はしばしば同一のストリートカルチャーとして語られてきたが、それぞれが辿ってきた歴史や積み重ねてきた知恵は決して単純な共通項に回収できるものではない。アナログな身体性やローカルなコミュニティから生まれた両カルチャーは、テクノロジーの進化とともにその表現や受容のされ方を変化させ、いまやデジタル時代ならではの新たな文脈の中で再解釈され続けている。そうした変遷の只中において、スケートボーディングと音楽という2つの軸を自然体で横断しながら、独自の視点でカルチャーを発信し続けているのが、ジャンルカ・クアリアーノ(Gianluca Quagliano)だ。
彼が主宰する『Skate Muzik(スケート・ミュージック)』は、即時性やアルゴリズムに支配されがちな現代において、あえて“ラジオ”という、一見すると時代に逆行するかのようなプラットフォームを拠点に、スケートボーディングと音楽が交差するリアルな温度感を丁寧に掬い上げている。スケートビデオのサウンドトラックにフォーカスした同番組は月に一度、英国イーストロンドンを拠点とするインターネットラジオ局「NTS Radio」にて配信され、レジェンドスケーターからシーン最前線のキーパーソンまでをゲストに迎え、コアなスケート論を展開。その内容はリスナーから高い支持を集めている。加えて今年2026年からは、ロンドン拠点のオンラインラジオ曲「Worldwide FM」でもレジデント放送予定だ。さらに、ラジオにとどまらず、各国で少数ながら展開されている関連アイテムも注目を集め、『Skate Muzik』はメディアとプロダクトの両面からカルチャーを体現する存在として、その存在感を確かなものにしている。
今回『Hypebeast』では、ジャンルカ・クアリアーノのクリエイティブの源流を辿るべくインタビューを敢行した。幼少期の原体験から現在の活動に至るまでの思考の変遷を、彼の言葉を手がかりに紐解きながら、『Skate Muzik』を通して提示されてきた価値観や美学に迫る。音楽とスケートボーディングという2つの軸を起点に、メディアやプロダクトへと広がる独自のアプローチと思想を読み解く本稿。彼の出身地であるイタリアで撮影されたポートフォリオとともに、その現在地を感じ取ってほしい。
自分で調べ、掘り下げていく姿勢が自然と身につき、それが今の考え方やスタンスを形づくる大きな要因になったと思っています
Hypebeast:『Hypebeast』読者に向けて自己紹介をお願いいたします。
ジャンルカ・クアリアーノ:ジャンルカ・クアリアーノです。イタリア・ミラノ出身で、スケートボーディングと音楽を軸にしたラジオプロジェクト『Skate Muzik』を主宰しています。
『Skate Muzik』はいつ、どのようにスタートしたのでしょうか?また、そのコンセプトについて教えてください。
『Skate Muzik』自体は2016年にスタートしましたが、アイデアそのものはそれ以前からずっと自分の中にありました。コンセプトはとてもシンプルで、僕自身が影響を受けてきたスケートビデオの中で使われている音楽を紹介することです。
スケートボーディングと音楽、それぞれへの関心はいつ、どのように生まれましたか?
僕がスケートボーディングに出会ったのは、音楽に深くのめり込んでいた知人の存在がきっかけでした。彼からオーリーのやり方を教わる一方で、さまざまなジャンルのカセットテープを手渡されることも多く、私の中では当初からスケートボーディングと音楽は切り離せないものとして結びついていました。そうした体験を重ねるなかで、スケートボーディングと音楽の両方に対する関心が自然と深まり、現在の活動へとつながっていったのだと思います。
なぜスケートビデオで使われている音楽にフォーカスするようになったのでしょうか?
子どもの頃から多くのスケートビデオを観て育ちましたが、そこで流れていた音楽は、僕にとって音楽的感性を育む大きな一部でした。当時はインターネットもなく、新しい音楽やカルチャーに出会うこと自体が今よりずっと難しかった。だからこそ、自分で調べ、掘り下げていく姿勢が自然と身につき、それが今の考え方やスタンスを形づくる大きな要因になったと思っています。
2024年6月には、Stone Island x New Balance NUMERIC 272が発売された際に、Skate MuzikがキュレーターとなりTiago Lemosのスケートビデオに着想を得たプレイリスト「SKATE MUZIK | STONE ISLAND」が発表されましたね。このプロジェクトはどのように実現したのでしょうか?
このプロジェクトは、Stone IslandのCMOであるオリバー(Oliver)と、共通の知人であるジェレミー・エルキンを介して知り合ったことがきっかけでした。当時、Stone Islandが手がけていたいくつかの音楽関連プロジェクトに個人的に強く惹かれており、さらにジェレミーが撮影を担当するティアゴ・レモスとのキャンペーンが進行していることも知っていました。そこで、Stone Islandが展開している「CURATED BY_」プレイリストのひとつを、自分がキュレーションできないかと提案したんです。その流れで、結果的に『Skate Muzik』のエピソードを別のプラットフォームで展開するような形になり、とても刺激的で充実したコラボレーションになりました。
番組のエピソードを見ていると、JAZZ 、90’s HIP HOP/R&Bといったジャンルと特に距離が近いことが伺えます。これらはスケートビデオにおいて切り離すことのできないジャンルであることは確かですが、これらの音楽と触れ合うようになったルーツは何でしょうか。
僕が初めて観たスケートビデオのひとつが、Blindの『Video Days』でした。とても幼い頃の体験でしたが、マーク・ゴンザレスがジョン・コルトレーンの『Traneing In』に乗せて滑るシーンは、今でも鮮明に記憶に残っています。その映像に衝撃を受けたことで、すぐにレコードショップに足を運び、ジョン・コルトレーンの作品を探しました。そこで手に取ったのが『A Love Supreme』で、あの瞬間に、音楽を聴くという行為そのものが、それまでとはまったく違うものになったと感じました。
同時期に、僕自身はヒップホップやハードコア/パンクのプロジェクトにも関わっていて、それらの影響は自然と共存していました。90年代前半から中盤にかけて、スケートビデオのサウンドもパンクロック中心の流れからヒップホップへと移行していき、映像表現やトリック、音楽が一体となって進化していった。その時代の変化はいまでも、自分が音楽を聴き、選び取る際の感覚に大きな影響を与え続けています。
現行の音楽シーンで気になっているアーティスト/レーベル/DJを教えてください。
この質問に答えているまさに今、NasとDJ Premier(DJ プレミア)の最新アルバム『Light-Years』を聴いています。ここ1年ほど、Nasは自身のレーベルを通じてMobb Deep(モブ ディープ)やGhostface(ゴーストフェイス)、Big L(ビッグ L)といった重要なアーティストの作品を継続的にリリースしてきましたが、その流れの中で生まれた今回のDJ Premierとのアルバムも含めて、あの一貫性はカルチャーに対する大きな貢献だと感じています。
『Skate Muzik』では、お気に入りのスケートビデオにフォーカスした回だけでなく、スケートビデオで使用されてきた音楽や、自分にとって特に影響の大きかったアーティストに焦点を当てたエピソードも制作してきました。これまでに、J Dilla(J・ディラ)やNujabes(ヌジャベス)をテーマにした回もあります。また、日本のジャズにも以前から強い関心があり、最近はThree Blind Mice(スリー・ブラインド・マイス)のようなレーベルをより深く掘り下げています。あと身近な仲間という意味では、友人であるClick-Head(クリックヘッド)とDoye-Tex(ドイテックス)による新作EPのリリースを楽しみにしていますし、Young OG Formiz(ヤング OG フォルミズ)の動きも常にチェックしています。The Night Skinny(ザ・ナイト・スキニー)も、いつも間違いない作品を準備しているアーティストですね。
番組として、スケートビデオのサウンドトラックを掘り直す意義は?
僕にとって、その意義は何よりもカルチャー的な側面にあります。スケートビデオで使われていた音楽は、幼い頃の自分の音楽的な嗜好を形づくり、いまでも音楽の聴き方に大きな影響を与え続けています。そうしたサウンドトラックを改めて振り返ることは、単なるノスタルジーではなく、ひとつのコミュニティが共有してきた共通のリファレンスを再確認する行為でもある。その“共通言語”や“共通の感覚”こそが、『Skate Muzik』という番組の核にあるものだと思っています。
これまで見てきたスケートビデオの中で、特に記憶に残っているものはありますか?
正直なところ、あまりにも多くの作品があるので、とても一つに絞れることはできません。挙げきれずに漏れてしまうものもきっとあると思います。そのうえで、特に初期に大きな影響を受けた作品として思い浮かぶのが『20 Shot Sequence』と『Trilogy』です。どちらもスタイルの面でも強いインパクトがあり、いま振り返っても重要なビデオだと感じています。『Trilogy』についてはジーノ・イアヌッチ(Gino Iannucci)とともに1エピソードを、『20 Shot Sequence』については2エピソードを『Skate Muzik』で制作しました。
また、トーマス・キャンベルによる『A Love Supreme』も特別な存在です。これは一般的なスケートビデオというより、アートフィルムとして語られることの多い作品ですが、モノクロの映像美、ジョン・コルトレーンのサウンドトラック、そして独自のビジュアル言語が強く印象に残っています。その延長線上にある作品として、Stereo Skateboardsの『Visual Sound』も挙げられます。モノクロの映像とUllulationの音楽が組み合わさることで、非常に明確な映像と音のアイデンティティが生まれていました。
ほかにも、短編ながら絶大な影響力を持ったTim & Harry(ティム&ハリー)による『Pack of Lies』は外せませんし、近年の作品では、僕の“兄弟”であるRat Ratz(ラット・ラッツ)の映像作品をとても誇りに思っています。また日本のスケートビデオにも以前から強い関心があり、友人の関口大地が手がけているプロジェクトも常に応援しています。現代のスケートビデオグラファーでは、ジョニー・ウィルソン(Johnny Wilson)にも注目しています。そして忘れてはならないのが、「William Strobeck(ウィリアム・ストローベック)」による『Cherry』です。これは『Skate Muzik』の最初のエピソードの題材にもなりました。
また、『Stallion』は僕の生まれ育った街を舞台にしていることもあり、個人的に特別な意味を持つ作品です。これらはあくまで一部に過ぎず、これまで影響を受けてきたスケートビデオについては、『Skate Muzik』のアーカイブを通して、より包括的に感じ取ってもらえるはずです。
Skate Muzikのエピソードを構成する際、ジャンル/ビデオ/アーティストを選ぶ基準はありますか?
基準はとてもシンプルで、過去のものも現在のものも含めて、純粋に自分が好きなビデオやアーティスト、音楽を選んでいます。時代や年代に関しても、特別なルールは設けていません。『Skate Muzik』で紹介しているものはすべて、自分自身の音楽観やスケートボーディング観に照らして「いま取り上げるべきだ」と感じたものだけです。多くの人に好かれているかどうかは、あまり気にしていません。もしそこを意識しすぎていたら、この番組自体を楽しめなくなってしまうと思います。
拡大すること自体が目的ではない
Skate MuzikとしてTシャツを作るようになった経緯を教えてください。
ラジオ番組を始めたのとほぼ同じタイミングで、Tシャツの制作もスタートしました。スケーターとして、グラフィックTシャツは昔から最も身近で大切なアイテムのひとつで、常に身に着けてきた存在です。番組を始めた当初から、その感覚をフィジカルな形に落とし込みたいという気持ちは自然と芽生えましたし、正直なところ、心の奥ではスケートカンパニーを立ち上げたいという思いもあったと思います。ただ当時は資金的な余裕もなく、完全に1人で動いていたので、すべてDIYのやり方で進めていました。その中で、Tシャツを作るという行為がいちばん自然なステップでしたね。実際、最初のラジオエピソードを公開してから、ほとんど間を置かずに制作を始めました。
初期のアイテムはどういったものを展開していたのでしょうか?
一番最初に作ったのは、スケートボードをするスヌーピーのイラストを大胆にブートレグした、白いTシャツです。初回の生産数は60枚で、すべて手書きでナンバリングを施し、そのほとんどを友人たちに配りました。それが、記念すべき最初の『Skate Muzik』のアイテムです。
これからTシャツ以外のアパレルを展開するプランはありますか?
実は、明確にプランがあるわけではありません。『Skate Muzik』は常に、オーガニックな流れの中で進んできました。これまでにも、キャップやフーディ、さらにはスケートボードのシリーズを制作したことがありますし、将来的にそれらを再び手がける可能性もあります。これらは完全にインディペンデントなプロジェクトなので、状況やタイミング次第な部分も大きいですね。拡大すること自体が目的ではなく、もし適切な機会が訪れたらアパレルに限らず、これまで考えたことのなかったアクセサリーなどにも挑戦してみたいと思っています。
アパレルアイテムの制作におけるインスピレーション源(映画、音楽、展示、人物)は?
参照しているもの自体は、映画や音楽、展覧会、人といった、ごく身近なカルチャーですが、制作のプロセスはとても自然なものです。何かを体系的に探しに行くというより、日常の中で本当に惹かれたものからアイデアが生まれることがほとんどですね。たとえば数年前、公開からかなり時間が経ってから映画『Ghost Dog』を劇場で観る機会がありました。帰宅して間もなく、その作品をモチーフにしたTシャツを作りたいというアイデアが自然と浮かんできたんです。その映画は自分にとって文化的な意味合いがとても強く、インスピレーションの結びつきも直感的なものでした。
『Skate Muzik』では、ムードボードを作ったり、スタイリストや外部のコンサルタント、アートディレクターといった存在と一緒に作業することはほとんどありません。最初から一貫して自分自身の好みを軸にしていて、その感覚は長年スケートボーディングと音楽のカルチャーに浸ってきた中で自然と形づくられてきたものです。そういう意味では、自分が扱っているリファレンスは、常にとてもパーソナルで、直接的な場所から生まれていると言えると思います。
昨年発表したSkate Muzik x ゴースト・ドッグカプセルコレクションのコレクションでは、ルックのフォトグラファーに関口大地を起用したり、PROVやThe Apartmentなど日本のショップにアイテムを卸していたりなど、日本のコミュニティとも親交が深い印象です。今に至るまで日本のコミュニティとの関係を築いた経緯を伺えますか?
大地は、1年の大半を離れて過ごしているものの僕にとってはとても大切な友人のひとりです。Skate Muzik x ゴースト・ドッグコレクションの東京でのビジュアルは、大地と篠塚虎一郎の2人が撮影を担当し、ショートクリップについては大地がディレクションから撮影まで手がけてくれました。
近いうちに予定している新しいSkate Muzikのプロジェクトでも、また一緒に取り組む予定です。ある意味で大地との関係性そのものが、僕と日本、そして東京のコミュニティとの関係を象徴しているように感じています。距離は離れていても、時間をかけて自然に育まれてきた関係で、そこには相互のリスペクトと親密さがあります。東京は、僕にとって特別な場所です。振り返ると、Skate MuzikのTシャツを世界で初めて取り扱ってくれたショップも、2017年に東京のPROVでした。ごく少量の、最初期のアイテムを扱ってもらったことをよく覚えています。現状に関しても、その頃から続く流れの延長線上にあるごく自然な出来事だと感じています。こうした関係性には、本当に感謝しかありません。もしこれを読んでくれている人がいたら、きっと僕が誰のことを指しているか分かっているはずです。ありがとう。また近いうちに、皆に会えることを楽しみにしています。
文化的な観点から、日本の好きな部分を教えてください。また、あなたの住むミラノとの違いは何でしょうか。
日本で最も印象に残っているのは、自分自身や他者、そして身の回りの環境に対して、人々が払っているリスペクトの深さです。日常生活の中に、誠実さや思いやりが自然に根付いていると感じています。たとえば、私の出身地であるミラノでは、カフェのテーブルに携帯電話を置いたまま席を離れたり、夜遅くにひとりで歩いたりすることは、場所によってはリスクを伴います。また、人と人との距離感に対する姿勢にも強く惹かれています。日本は閉鎖的、あるいは控えめな国だと捉えられることもありますが、私にとっては、それは大切な文化や価値観を守るためのひとつのあり方だと感じています。もちろん、日本という国をすべて理解しているとは言えませんが、これまでに触れてきた体験だけでも、深い敬意を抱くには十分でした。特に、音楽やスケートボーディング、ファッションといったカルチャーに対する向き合い方からは、多くのインスピレーションを受けています。日本のカルチャーは、ストリートファッションの進化においても非常に重要な役割を果たしてきましたし、西洋の多くのブランドに多大な影響を与えてきたことは、疑いようのない事実だと思います。
日本のお気に入りスポットはどこですか?
すべてを明かすつもりはありませんが(笑)、東京は私にとってとても特別な存在で、強い親近感を覚える街です。昼と夜、賑やかなエリアと静かで親密な一角といったように、さまざまな表情を併せ持っているところに大きな魅力を感じています。東京に滞在しているときは、Beat Café(ビートカフェ)に立ち寄ってカトマンに“チャオ(ciao)”と挨拶するのが楽しみのひとつですし、JBS Café(JBS カフェ)では純粋に音楽を聴く時間を過ごすことが多いですね。また、The Breakfast Club(ブレックファスト・クラブ)はリラックスして食事ができるお気に入りの場所で、昨年はそこで小さなSkate Muzikのパーティーも開催しました。とても楽しい時間になりましたし、パーティーに協力してくれたMama Luli、Kunichi、そして足を運んでくれた皆さんには感謝しています。基本的には、東京にいる友人たちに身を委ねることが多いです。彼らが自分のお気に入りの場所に連れて行ってくれて、観光ガイドではなかなか見えない、より日常的でリアルな東京の姿を見せてくれる。その時間が、僕にとっては何より貴重ですね。
今後予定しているプロジェクト等があれば教えてください。
2026年は、Skate Muzikにとって10周年という大きな節目の年になります。始めたのはつい昨日のことのようにも感じますし、一方で、ようやく人々にSkate Muzikを紹介し始めたばかりのような感覚もあります。近々、新しいSkate Muzikのマーチャンダイズ・コレクションをリリースする予定です。今回は、私自身が心からリスペクトしている人たちとのコラボレーションを軸に構成しました。Gregory Simmons(グレゴリー・シモンズ)、Eli Gesner(イーライ・ゲスナー)、Very Special(ベリースペシャル)に加え、Gang StarrのGuru(グールー)の息子であるKeith Elam(キース・エラム)と共に制作した、Jazzmatazzにインスパイアされたカプセルコレクションも含まれています。また、Gilles Peterson(ジャイルス・ピーターソン)が設立したWorldwide FMにて、新たなラジオ・レジデンシーもスタートしました。彼は以前から世界の音楽シーンにおいて強い敬意を抱いてきた存在であり、そのプラットフォームの一員として活動できることを、とても光栄に感じています。
最後に、あなたはSkate Muzikを通して世の中へ何を伝えていきたいですか?
Skate Muzikは、とてもシンプルなかたちで始まりました。最初から大きな計画があったわけではなく、ほとんど自宅からスタートしたプロジェクトです。もしこの活動を通して何かを感じ取ってもらえるとしたら、「本当に大切だと思うものに誠実に向き合うことが、確かな違いを生み出す」というメッセージだと思います。
Skate Muzik
Skate Muzikは、ミラノを拠点に活動するジャンルカ・クアリアーノ(Gianluca Quagliano)によるプロジェクト。2016年にスタートし、スケートビデオに使用されてきた音楽を起点に、ラジオ番組、プレイリスト、アパレル、そしてカルチャー全体へとその活動領域を広げてきた。ジャズや90年代ヒップホップ/R&Bといったジャンルを横断しながら、スケートボーディングと音楽が持つ文化的背景や記憶を掘り下げ、個人的な視点を通して再構築するそのアプローチは、多くの共感を集めている。DIY精神を軸に、あくまで自身の感覚とリアルな体験を大切にしてきたSkate Muzikは、東京をはじめとする日本のコミュニティとも深い関係性を築いてきた。2026年には10周年を迎え、音楽・スケートボーディング・ファッションを横断する独立したカルチャープラットフォームとして、今なお進化を続けている。
in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing
tags from
スケートボーディングと音楽。両者はしばしば同一のストリートカルチャーとして語られてきたが、それぞれが辿ってきた歴史や積み重ねてきた知恵は決して単純な共通項に回収できるものではない。アナログな身体性やローカルなコミュニティから生まれた両カルチャーは、テクノロジーの進化とともにその表現や受容のされ方を変化させ、いまやデジタル時代ならではの新たな文脈の中で再解釈され続けている。そうした変遷の只中において、スケートボーディングと音楽という2つの軸を自然体で横断しながら、独自の視点でカルチャーを発信し続けているのが、ジャンルカ・クアリアーノ(Gianluca Quagliano)だ。
彼が主宰する『Skate Muzik(スケート・ミュージック)』は、即時性やアルゴリズムに支配されがちな現代において、あえて“ラジオ”という、一見すると時代に逆行するかのようなプラットフォームを拠点に、スケートボーディングと音楽が交差するリアルな温度感を丁寧に掬い上げている。スケートビデオのサウンドトラックにフォーカスした同番組は月に一度、英国イーストロンドンを拠点とするインターネットラジオ局「NTS Radio」にて配信され、レジェンドスケーターからシーン最前線のキーパーソンまでをゲストに迎え、コアなスケート論を展開。その内容はリスナーから高い支持を集めている。加えて今年2026年からは、ロンドン拠点のオンラインラジオ曲「Worldwide FM」でもレジデント放送予定だ。さらに、ラジオにとどまらず、各国で少数ながら展開されている関連アイテムも注目を集め、『Skate Muzik』はメディアとプロダクトの両面からカルチャーを体現する存在として、その存在感を確かなものにしている。
今回『Hypebeast』では、ジャンルカ・クアリアーノのクリエイティブの源流を辿るべくインタビューを敢行した。幼少期の原体験から現在の活動に至るまでの思考の変遷を、彼の言葉を手がかりに紐解きながら、『Skate Muzik』を通して提示されてきた価値観や美学に迫る。音楽とスケートボーディングという2つの軸を起点に、メディアやプロダクトへと広がる独自のアプローチと思想を読み解く本稿。彼の出身地であるイタリアで撮影されたポートフォリオとともに、その現在地を感じ取ってほしい。
自分で調べ、掘り下げていく姿勢が自然と身につき、それが今の考え方やスタンスを形づくる大きな要因になったと思っています
Hypebeast:『Hypebeast』読者に向けて自己紹介をお願いいたします。
ジャンルカ・クアリアーノ:ジャンルカ・クアリアーノです。イタリア・ミラノ出身で、スケートボーディングと音楽を軸にしたラジオプロジェクト『Skate Muzik』を主宰しています。
『Skate Muzik』はいつ、どのようにスタートしたのでしょうか?また、そのコンセプトについて教えてください。
『Skate Muzik』自体は2016年にスタートしましたが、アイデアそのものはそれ以前からずっと自分の中にありました。コンセプトはとてもシンプルで、僕自身が影響を受けてきたスケートビデオの中で使われている音楽を紹介することです。
スケートボーディングと音楽、それぞれへの関心はいつ、どのように生まれましたか?
僕がスケートボーディングに出会ったのは、音楽に深くのめり込んでいた知人の存在がきっかけでした。彼からオーリーのやり方を教わる一方で、さまざまなジャンルのカセットテープを手渡されることも多く、私の中では当初からスケートボーディングと音楽は切り離せないものとして結びついていました。そうした体験を重ねるなかで、スケートボーディングと音楽の両方に対する関心が自然と深まり、現在の活動へとつながっていったのだと思います。
なぜスケートビデオで使われている音楽にフォーカスするようになったのでしょうか?
子どもの頃から多くのスケートビデオを観て育ちましたが、そこで流れていた音楽は、僕にとって音楽的感性を育む大きな一部でした。当時はインターネットもなく、新しい音楽やカルチャーに出会うこと自体が今よりずっと難しかった。だからこそ、自分で調べ、掘り下げていく姿勢が自然と身につき、それが今の考え方やスタンスを形づくる大きな要因になったと思っています。
2024年6月には、Stone Island x New Balance NUMERIC 272が発売された際に、Skate MuzikがキュレーターとなりTiago Lemosのスケートビデオに着想を得たプレイリスト「SKATE MUZIK | STONE ISLAND」が発表されましたね。このプロジェクトはどのように実現したのでしょうか?
このプロジェクトは、Stone IslandのCMOであるオリバー(Oliver)と、共通の知人であるジェレミー・エルキンを介して知り合ったことがきっかけでした。当時、Stone Islandが手がけていたいくつかの音楽関連プロジェクトに個人的に強く惹かれており、さらにジェレミーが撮影を担当するティアゴ・レモスとのキャンペーンが進行していることも知っていました。そこで、Stone Islandが展開している「CURATED BY_」プレイリストのひとつを、自分がキュレーションできないかと提案したんです。その流れで、結果的に『Skate Muzik』のエピソードを別のプラットフォームで展開するような形になり、とても刺激的で充実したコラボレーションになりました。
番組のエピソードを見ていると、JAZZ 、90’s HIP HOP/R&Bといったジャンルと特に距離が近いことが伺えます。これらはスケートビデオにおいて切り離すことのできないジャンルであることは確かですが、これらの音楽と触れ合うようになったルーツは何でしょうか。
僕が初めて観たスケートビデオのひとつが、Blindの『Video Days』でした。とても幼い頃の体験でしたが、マーク・ゴンザレスがジョン・コルトレーンの『Traneing In』に乗せて滑るシーンは、今でも鮮明に記憶に残っています。その映像に衝撃を受けたことで、すぐにレコードショップに足を運び、ジョン・コルトレーンの作品を探しました。そこで手に取ったのが『A Love Supreme』で、あの瞬間に、音楽を聴くという行為そのものが、それまでとはまったく違うものになったと感じました。
同時期に、僕自身はヒップホップやハードコア/パンクのプロジェクトにも関わっていて、それらの影響は自然と共存していました。90年代前半から中盤にかけて、スケートビデオのサウンドもパンクロック中心の流れからヒップホップへと移行していき、映像表現やトリック、音楽が一体となって進化していった。その時代の変化はいまでも、自分が音楽を聴き、選び取る際の感覚に大きな影響を与え続けています。
現行の音楽シーンで気になっているアーティスト/レーベル/DJを教えてください。
この質問に答えているまさに今、NasとDJ Premier(DJ プレミア)の最新アルバム『Light-Years』を聴いています。ここ1年ほど、Nasは自身のレーベルを通じてMobb Deep(モブ ディープ)やGhostface(ゴーストフェイス)、Big L(ビッグ L)といった重要なアーティストの作品を継続的にリリースしてきましたが、その流れの中で生まれた今回のDJ Premierとのアルバムも含めて、あの一貫性はカルチャーに対する大きな貢献だと感じています。
『Skate Muzik』では、お気に入りのスケートビデオにフォーカスした回だけでなく、スケートビデオで使用されてきた音楽や、自分にとって特に影響の大きかったアーティストに焦点を当てたエピソードも制作してきました。これまでに、J Dilla(J・ディラ)やNujabes(ヌジャベス)をテーマにした回もあります。また、日本のジャズにも以前から強い関心があり、最近はThree Blind Mice(スリー・ブラインド・マイス)のようなレーベルをより深く掘り下げています。あと身近な仲間という意味では、友人であるClick-Head(クリックヘッド)とDoye-Tex(ドイテックス)による新作EPのリリースを楽しみにしていますし、Young OG Formiz(ヤング OG フォルミズ)の動きも常にチェックしています。The Night Skinny(ザ・ナイト・スキニー)も、いつも間違いない作品を準備しているアーティストですね。
番組として、スケートビデオのサウンドトラックを掘り直す意義は?
僕にとって、その意義は何よりもカルチャー的な側面にあります。スケートビデオで使われていた音楽は、幼い頃の自分の音楽的な嗜好を形づくり、いまでも音楽の聴き方に大きな影響を与え続けています。そうしたサウンドトラックを改めて振り返ることは、単なるノスタルジーではなく、ひとつのコミュニティが共有してきた共通のリファレンスを再確認する行為でもある。その“共通言語”や“共通の感覚”こそが、『Skate Muzik』という番組の核にあるものだと思っています。
これまで見てきたスケートビデオの中で、特に記憶に残っているものはありますか?
正直なところ、あまりにも多くの作品があるので、とても一つに絞れることはできません。挙げきれずに漏れてしまうものもきっとあると思います。そのうえで、特に初期に大きな影響を受けた作品として思い浮かぶのが『20 Shot Sequence』と『Trilogy』です。どちらもスタイルの面でも強いインパクトがあり、いま振り返っても重要なビデオだと感じています。『Trilogy』についてはジーノ・イアヌッチ(Gino Iannucci)とともに1エピソードを、『20 Shot Sequence』については2エピソードを『Skate Muzik』で制作しました。
また、トーマス・キャンベルによる『A Love Supreme』も特別な存在です。これは一般的なスケートビデオというより、アートフィルムとして語られることの多い作品ですが、モノクロの映像美、ジョン・コルトレーンのサウンドトラック、そして独自のビジュアル言語が強く印象に残っています。その延長線上にある作品として、Stereo Skateboardsの『Visual Sound』も挙げられます。モノクロの映像とUllulationの音楽が組み合わさることで、非常に明確な映像と音のアイデンティティが生まれていました。
ほかにも、短編ながら絶大な影響力を持ったTim & Harry(ティム&ハリー)による『Pack of Lies』は外せませんし、近年の作品では、僕の“兄弟”であるRat Ratz(ラット・ラッツ)の映像作品をとても誇りに思っています。また日本のスケートビデオにも以前から強い関心があり、友人の関口大地が手がけているプロジェクトも常に応援しています。現代のスケートビデオグラファーでは、ジョニー・ウィルソン(Johnny Wilson)にも注目しています。そして忘れてはならないのが、「William Strobeck(ウィリアム・ストローベック)」による『Cherry』です。これは『Skate Muzik』の最初のエピソードの題材にもなりました。
また、『Stallion』は僕の生まれ育った街を舞台にしていることもあり、個人的に特別な意味を持つ作品です。これらはあくまで一部に過ぎず、これまで影響を受けてきたスケートビデオについては、『Skate Muzik』のアーカイブを通して、より包括的に感じ取ってもらえるはずです。
Skate Muzikのエピソードを構成する際、ジャンル/ビデオ/アーティストを選ぶ基準はありますか?
基準はとてもシンプルで、過去のものも現在のものも含めて、純粋に自分が好きなビデオやアーティスト、音楽を選んでいます。時代や年代に関しても、特別なルールは設けていません。『Skate Muzik』で紹介しているものはすべて、自分自身の音楽観やスケートボーディング観に照らして「いま取り上げるべきだ」と感じたものだけです。多くの人に好かれているかどうかは、あまり気にしていません。もしそこを意識しすぎていたら、この番組自体を楽しめなくなってしまうと思います。
拡大すること自体が目的ではない
Skate MuzikとしてTシャツを作るようになった経緯を教えてください。
ラジオ番組を始めたのとほぼ同じタイミングで、Tシャツの制作もスタートしました。スケーターとして、グラフィックTシャツは昔から最も身近で大切なアイテムのひとつで、常に身に着けてきた存在です。番組を始めた当初から、その感覚をフィジカルな形に落とし込みたいという気持ちは自然と芽生えましたし、正直なところ、心の奥ではスケートカンパニーを立ち上げたいという思いもあったと思います。ただ当時は資金的な余裕もなく、完全に1人で動いていたので、すべてDIYのやり方で進めていました。その中で、Tシャツを作るという行為がいちばん自然なステップでしたね。実際、最初のラジオエピソードを公開してから、ほとんど間を置かずに制作を始めました。
初期のアイテムはどういったものを展開していたのでしょうか?
一番最初に作ったのは、スケートボードをするスヌーピーのイラストを大胆にブートレグした、白いTシャツです。初回の生産数は60枚で、すべて手書きでナンバリングを施し、そのほとんどを友人たちに配りました。それが、記念すべき最初の『Skate Muzik』のアイテムです。
これからTシャツ以外のアパレルを展開するプランはありますか?
実は、明確にプランがあるわけではありません。『Skate Muzik』は常に、オーガニックな流れの中で進んできました。これまでにも、キャップやフーディ、さらにはスケートボードのシリーズを制作したことがありますし、将来的にそれらを再び手がける可能性もあります。これらは完全にインディペンデントなプロジェクトなので、状況やタイミング次第な部分も大きいですね。拡大すること自体が目的ではなく、もし適切な機会が訪れたらアパレルに限らず、これまで考えたことのなかったアクセサリーなどにも挑戦してみたいと思っています。
アパレルアイテムの制作におけるインスピレーション源(映画、音楽、展示、人物)は?
参照しているもの自体は、映画や音楽、展覧会、人といった、ごく身近なカルチャーですが、制作のプロセスはとても自然なものです。何かを体系的に探しに行くというより、日常の中で本当に惹かれたものからアイデアが生まれることがほとんどですね。たとえば数年前、公開からかなり時間が経ってから映画『Ghost Dog』を劇場で観る機会がありました。帰宅して間もなく、その作品をモチーフにしたTシャツを作りたいというアイデアが自然と浮かんできたんです。その映画は自分にとって文化的な意味合いがとても強く、インスピレーションの結びつきも直感的なものでした。
『Skate Muzik』では、ムードボードを作ったり、スタイリストや外部のコンサルタント、アートディレクターといった存在と一緒に作業することはほとんどありません。最初から一貫して自分自身の好みを軸にしていて、その感覚は長年スケートボーディングと音楽のカルチャーに浸ってきた中で自然と形づくられてきたものです。そういう意味では、自分が扱っているリファレンスは、常にとてもパーソナルで、直接的な場所から生まれていると言えると思います。
昨年発表したSkate Muzik x ゴースト・ドッグカプセルコレクションのコレクションでは、ルックのフォトグラファーに関口大地を起用したり、PROVやThe Apartmentなど日本のショップにアイテムを卸していたりなど、日本のコミュニティとも親交が深い印象です。今に至るまで日本のコミュニティとの関係を築いた経緯を伺えますか?
大地は、1年の大半を離れて過ごしているものの僕にとってはとても大切な友人のひとりです。Skate Muzik x ゴースト・ドッグコレクションの東京でのビジュアルは、大地と篠塚虎一郎の2人が撮影を担当し、ショートクリップについては大地がディレクションから撮影まで手がけてくれました。
近いうちに予定している新しいSkate Muzikのプロジェクトでも、また一緒に取り組む予定です。ある意味で大地との関係性そのものが、僕と日本、そして東京のコミュニティとの関係を象徴しているように感じています。距離は離れていても、時間をかけて自然に育まれてきた関係で、そこには相互のリスペクトと親密さがあります。東京は、僕にとって特別な場所です。振り返ると、Skate MuzikのTシャツを世界で初めて取り扱ってくれたショップも、2017年に東京のPROVでした。ごく少量の、最初期のアイテムを扱ってもらったことをよく覚えています。現状に関しても、その頃から続く流れの延長線上にあるごく自然な出来事だと感じています。こうした関係性には、本当に感謝しかありません。もしこれを読んでくれている人がいたら、きっと僕が誰のことを指しているか分かっているはずです。ありがとう。また近いうちに、皆に会えることを楽しみにしています。
文化的な観点から、日本の好きな部分を教えてください。また、あなたの住むミラノとの違いは何でしょうか。
日本で最も印象に残っているのは、自分自身や他者、そして身の回りの環境に対して、人々が払っているリスペクトの深さです。日常生活の中に、誠実さや思いやりが自然に根付いていると感じています。たとえば、私の出身地であるミラノでは、カフェのテーブルに携帯電話を置いたまま席を離れたり、夜遅くにひとりで歩いたりすることは、場所によってはリスクを伴います。また、人と人との距離感に対する姿勢にも強く惹かれています。日本は閉鎖的、あるいは控えめな国だと捉えられることもありますが、私にとっては、それは大切な文化や価値観を守るためのひとつのあり方だと感じています。もちろん、日本という国をすべて理解しているとは言えませんが、これまでに触れてきた体験だけでも、深い敬意を抱くには十分でした。特に、音楽やスケートボーディング、ファッションといったカルチャーに対する向き合い方からは、多くのインスピレーションを受けています。日本のカルチャーは、ストリートファッションの進化においても非常に重要な役割を果たしてきましたし、西洋の多くのブランドに多大な影響を与えてきたことは、疑いようのない事実だと思います。
日本のお気に入りスポットはどこですか?
すべてを明かすつもりはありませんが(笑)、東京は私にとってとても特別な存在で、強い親近感を覚える街です。昼と夜、賑やかなエリアと静かで親密な一角といったように、さまざまな表情を併せ持っているところに大きな魅力を感じています。東京に滞在しているときは、Beat Café(ビートカフェ)に立ち寄ってカトマンに“チャオ(ciao)”と挨拶するのが楽しみのひとつですし、JBS Café(JBS カフェ)では純粋に音楽を聴く時間を過ごすことが多いですね。また、The Breakfast Club(ブレックファスト・クラブ)はリラックスして食事ができるお気に入りの場所で、昨年はそこで小さなSkate Muzikのパーティーも開催しました。とても楽しい時間になりましたし、パーティーに協力してくれたMama Luli、Kunichi、そして足を運んでくれた皆さんには感謝しています。基本的には、東京にいる友人たちに身を委ねることが多いです。彼らが自分のお気に入りの場所に連れて行ってくれて、観光ガイドではなかなか見えない、より日常的でリアルな東京の姿を見せてくれる。その時間が、僕にとっては何より貴重ですね。
今後予定しているプロジェクト等があれば教えてください。
2026年は、Skate Muzikにとって10周年という大きな節目の年になります。始めたのはつい昨日のことのようにも感じますし、一方で、ようやく人々にSkate Muzikを紹介し始めたばかりのような感覚もあります。近々、新しいSkate Muzikのマーチャンダイズ・コレクションをリリースする予定です。今回は、私自身が心からリスペクトしている人たちとのコラボレーションを軸に構成しました。Gregory Simmons(グレゴリー・シモンズ)、Eli Gesner(イーライ・ゲスナー)、Very Special(ベリースペシャル)に加え、Gang StarrのGuru(グールー)の息子であるKeith Elam(キース・エラム)と共に制作した、Jazzmatazzにインスパイアされたカプセルコレクションも含まれています。また、Gilles Peterson(ジャイルス・ピーターソン)が設立したWorldwide FMにて、新たなラジオ・レジデンシーもスタートしました。彼は以前から世界の音楽シーンにおいて強い敬意を抱いてきた存在であり、そのプラットフォームの一員として活動できることを、とても光栄に感じています。
最後に、あなたはSkate Muzikを通して世の中へ何を伝えていきたいですか?
Skate Muzikは、とてもシンプルなかたちで始まりました。最初から大きな計画があったわけではなく、ほとんど自宅からスタートしたプロジェクトです。もしこの活動を通して何かを感じ取ってもらえるとしたら、「本当に大切だと思うものに誠実に向き合うことが、確かな違いを生み出す」というメッセージだと思います。
Skate Muzik
Skate Muzikは、ミラノを拠点に活動するジャンルカ・クアリアーノ(Gianluca Quagliano)によるプロジェクト。2016年にスタートし、スケートビデオに使用されてきた音楽を起点に、ラジオ番組、プレイリスト、アパレル、そしてカルチャー全体へとその活動領域を広げてきた。ジャズや90年代ヒップホップ/R&Bといったジャンルを横断しながら、スケートボーディングと音楽が持つ文化的背景や記憶を掘り下げ、個人的な視点を通して再構築するそのアプローチは、多くの共感を集めている。DIY精神を軸に、あくまで自身の感覚とリアルな体験を大切にしてきたSkate Muzikは、東京をはじめとする日本のコミュニティとも深い関係性を築いてきた。2026年には10周年を迎え、音楽・スケートボーディング・ファッションを横断する独立したカルチャープラットフォームとして、今なお進化を続けている。
and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.