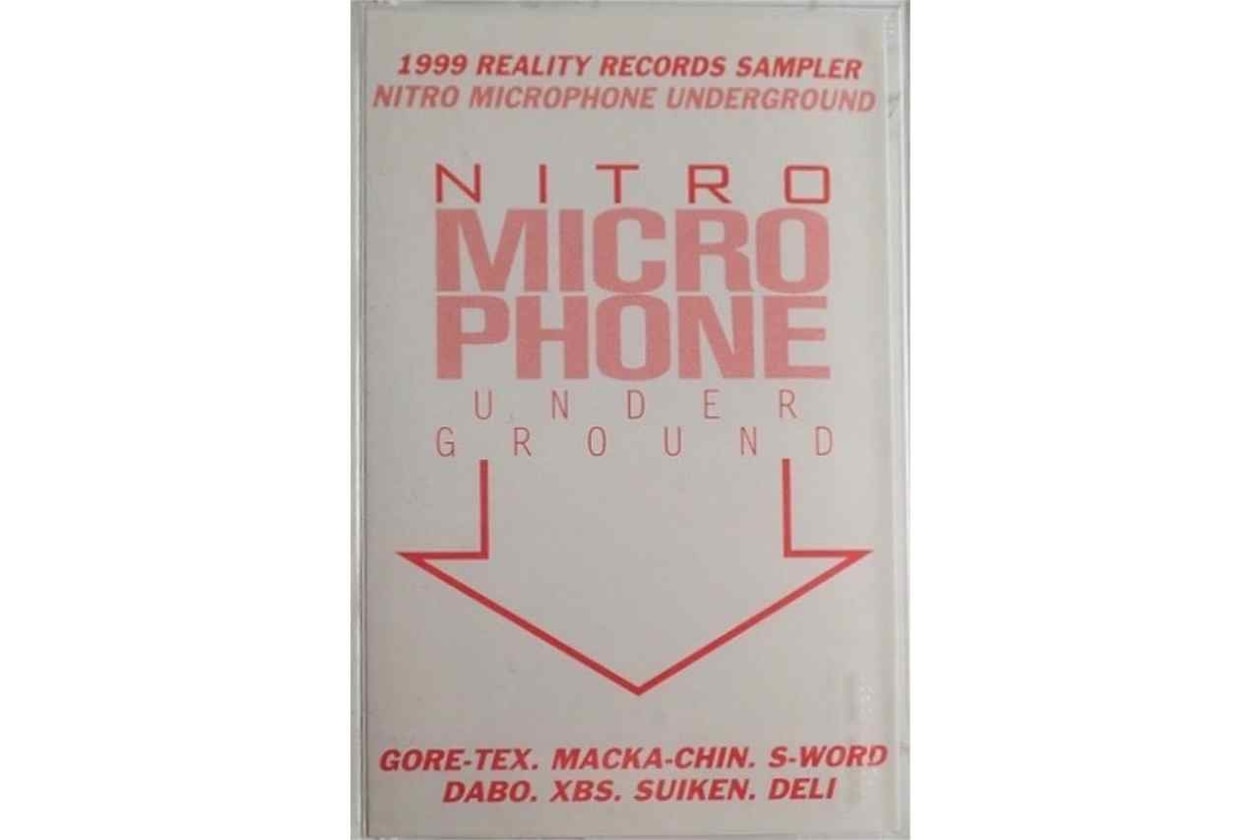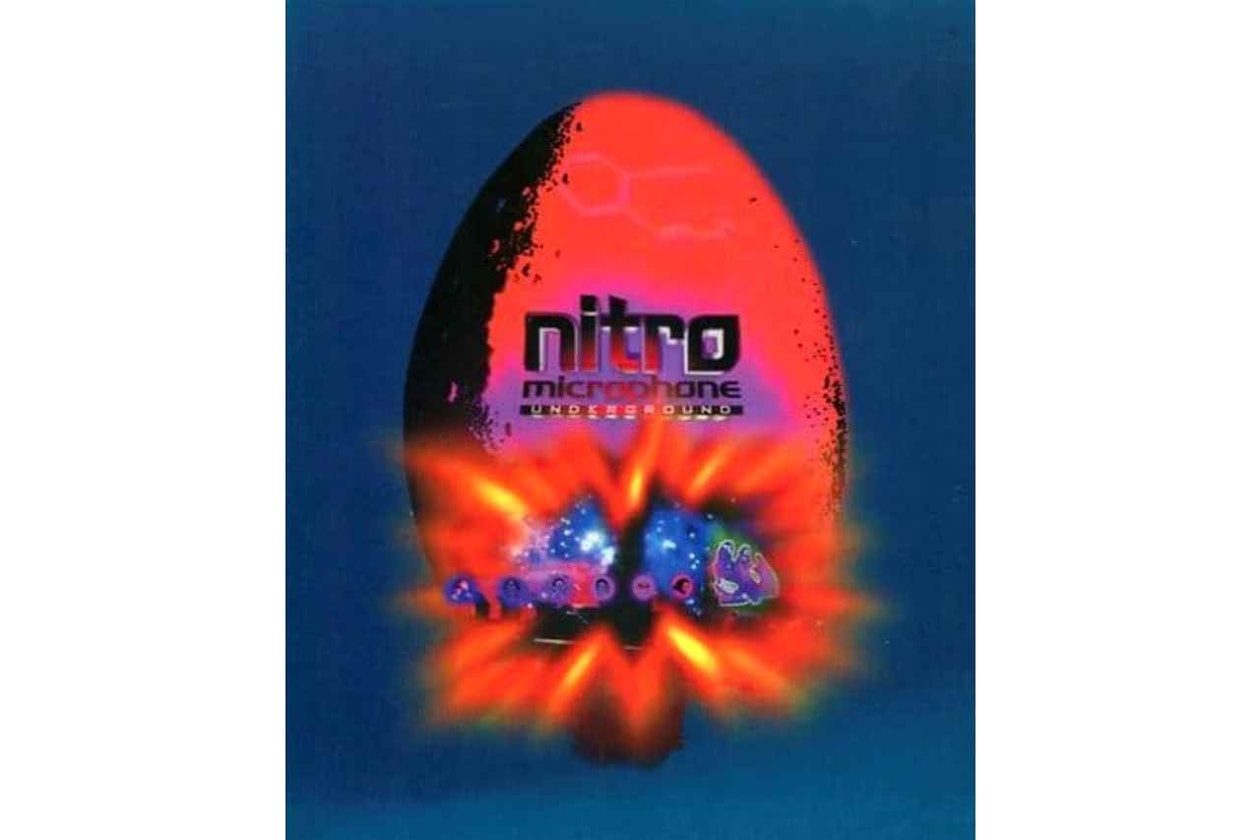Rewrite
日本のヒップホップは、黎明期から長らく東京を中心に歴史を築き上げてきた。ブラックミュージックに傾倒し、ラップというアートフォームに憧れを抱いた若者は、未知のジャンルへの可能性と、体感したことのない洗練されたスタイルに胸を高鳴らせる。1990年代中期、『DA.YO.NE』や『今夜はブキー・バック』が巷を席巻した第一次ラップブームが訪れた時代 ── テレビや新聞、情報誌などのマスメディアが伝聞する情報に世の中は沸き立ち、「ヒップホップ」というワードが持てはやされる時代が到来した。しかし一方では、水面下で巻き起こる「何がリアルで何がフェイクか」論争が顕在化し、「これが本当にヒップホップなのか」と疑念を抱く者も現れ、この時代から自らのセンスでリアルをジャッジする審美眼と、セルアウト(商業主義)を忌み嫌う文化は並行して走り続ける。そんなことはお構いなしにオーバーグラウンドでは「チェケラッチョ」という言葉がミーム化し、ラップが常態化していく状況とは裏腹に、アンダーグラウンドではそんな言葉を用いることなく、日々スキルを磨く面々が切磋琢磨していた。
それからほどなくして、渋谷のクラブ『CAVE』では、セルアウトの動向など見向きもせぬ面々が新たなイベント「A BAOA QU」を始動させ、徐々に耳目を集めるパーティとなっていた。大袈裟に表現するまでもなく、そこに集う顔ぶれは、「誰よりも自分が一番イケている」精神を宿す音楽/クラブ/ファッション業界に従事する面々、そしてDJ、ダンサー、ラッパーたちだ。その時代「現場」と呼ばれるクラブという空間は、自らのセンスを自負する者たちが同じテンションで邁進できる仲間を無自覚ながら探す場所としても機能していた。SNSはおろか、インターネットすらままならない時代において、うまい具合にフィールする人間を探し出すことは容易なことでないが、その空間でのちに誕生するNITRO MICROPHONE UNDERGROUND(ニトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンド)の原形が形成されることになる──。本稿ではメンバーや関係者の言葉を引用しながら、ニトロ結成前から活動休止、そして再始動から現在に至るまでの四半世紀における歴史を振り返っていく。MACKA-CHIN(マッカチン)の回想から始めよう。
「ニトロはキングギドラや雷、RHYMESTER(ライムスター)みたいに『グループを結成して曲を作って、アンダーグラウンドでライブ活動!』とか考えてスタートしたわけじゃないんですよ。ニトロ結成前のつながりで言えば、僕は当時原宿で働いてたんだけど、GORE-TEX(ゴアテックス)とS-WORD(スウォード)が渋谷で働いてて、XBS(エックスビーエス)とは高校で同級生。SUIKEN(スイケン)とDABO(ダボ)はDJ HAZIME(DJ ハジメ)やK-BOMB(ケーボン)とチームを組んで西麻布でイベントをやっていたのね。みんながそれぞれヒップホップが好きで、知り合いが働いてる店やクラブを回ることで自然と交流を深めていたんだと思う。そのぐらいのタイミングになるのかな、先輩から『CAVEでなんかイベントやれよ』って誘われて。月イチ第一水曜日のイベントだったんだけど、回を重ねるごとに人がパンパンになってきてね。ただ、この時点でDELI(デリ)とBIGZAM(ビグザム)とはまだ合流はしていなかったかな」(MACKA-CHIN)
今では到底考えられないが、トラックを制作できる機材はもちろん、レーベルと契約しなければレコーディング環境すら整えるのが困難な時代。そのため当時のライブは、海外アーティストの12インチに収録されたインストをオケに自作のラップを乗せるスタイルが主流で、その「オケを何にするか(しているか)」で、センスが見極められた時代と言っても過言ではない。そんなイベントの活況を耳にした『Manhattan Records(マンハッタン・レコード)』や『CISCO(シスコ)』といった宇田川町の代名詞でもあるレコードショップのスタッフも、イベントに足を運ぶようになる。あらゆるカルチャーの坩堝となった空間で、イベントを盛り上げる30人前後のメンバーは“約 NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”として自然と結束を固めていく。その好機を見逃さなかったのが、「一緒に曲を作らないか?」とMACKA-CHINに声をかけた元『Manhattan Records』、後にニトロのソロ/グループ作品をリリースする「Reality Records(リアリティ・レコーズ)」のエグゼクティブ・プロデューサー/A&Rを務める「株式会社レキシントン」の前川和昭氏だ。しかし、セルアウト拒絶反応時代も相まってか、約ニトロのメンバーの中には「デビューとかマジどうでもいい」と見向きもしない勢すら存在したという。そして、活況や好機とは裏腹に「まっとうに働くべき年齢」という壁に直面し、強固となった結束を就職のためにほどかざるを得ない世代も現れ、結果的に残ったメンバーがニトロの原形を担うことになる。
「渋谷宇田川発」というリアリティ
1990年代、海外ではWu-Tang Clan(ウータン・クラン)やBoot Camp Clik(ブート・キャンプ・クリック)、D.I.T.C.(ディーアイティーシー)など、日本でもLAMP EYE『証言』に象徴されるように、大所帯で回していくマイクリレーには言葉で説明しきれないほどのエネルギーが感じ取られた。それらに倣うように、「A BAOA QU」に出演していたMACKA-CHIN、S-WORD、GORE-TEX、SUIKENによる4人のマイクリレー『REQUIEM』(99年発売。プロデュースはDJ WATARAI)が「Reality Records」からリリースされるまで、それほど時間は要さなかった。前述した前川氏が当時を振り返る。
「マンハッタンで働き始めた94年当時は、US/UK直送のヒップホップ/R&Bを中心に扱っていたんですが、僕がMICROPHONE PAGER(マイクロフォン・ペイジャー)や雷が大好きだったこともあり、日本語ラップも積極的に取り扱うようになっていきました。並行して96年頃からBEN THE ACE(ベン ザ エース)さんのレーベル SPELLBOUND(スペルバウンド)や、MURO(ムロ)さんのレーベル INCREDIBLE(インクレディブル)で裏方をされていた先輩の手伝いもしていたんですが、マンハッタンでもレーベル事業をやりたい気運が高まっていた98年、創業者である平川(雅夫)さんから『スタジオを作るからレーベル始めないか?』と言われたのがReality Recordsの始まりです。
その頃ヨシテル(MACKA-CHIN)が原宿のレコ屋で働いていたんですけど、昼間会いに行ってメシを食いながらいろいろ話したのを覚えています。そこで『トラ(GORE-TEX)のレコーディングの合間に録ったデモがあるから、それを出さない?』と言われた曲が、後にRealityからリリースする『REQUIEM』。設立当時の方針は『自分が好きなアーティストをリリースする』という、至ってシンプルなものでした」(前川和昭)
前述した通り、まだニトロの原形であった理由から『REQUIEM』のクレジットは「S-WORD/MACKA-CHIN/GORE-TEX」となっている(客演としてSUIKENも参加しているがクレジットは未表記)。前川氏が述べたように、レーベル事業のみならず、日本語ラップそのものの機運が高まっていた時代でもあり、同時に『REQUIEM』の12インチが8000枚即完という結果は、日本語ラップの機運という枠をすら越えて、宇田川町がカルチャーの発信源となるきっかけも作り出した。
当時の宇田川町の雰囲気を体感した者なら、良い意味でも悪い意味でも記憶から消えることのない濃すぎる思い出があるだろう。例えば、宇田川町に所狭しとひしめき合うレコードショップや洋服屋のスタッフはいつも横柄で、サービス業の風上にも置けたものじゃない。店内では客をないがしろにするスタッフが悪ノリ内輪ノリで盛り上がっている。だが、必死で最先端の情報を求める若者にとっては、その状況すらある種有益な障壁であり、誰よりも早くイケてるアナログや洋服を手にしかたかったはずだ。とはいえ、思い返してみても、勤務するショップスタッフの知識やセンスに疑う余地はなく、その威圧的かつ塩対応だったからこそ、誰もが貪欲になれた恩恵もある。ニトロは、その感覚をもっとも体現・具現化した宇田川発(初)のヒップホップグループだったとすら思う。
これはレコードショップに限った話だが、誰よりも早く入手すべく、その物欲を高める要素に「Promotional Use Only, Not For Sale」という文字列がある。「インストはプロモにしか収録されていない」「リミックスはプロモにだけ収録されている」「この12インチはプロモでしか存在しない」 ── この文字列の恐ろしいほどの引力は、『REQUIEM』リリースからほどなくして、初のNITRO MICROPHONE UNDERGROUND名義として販売された『Nitro Works』(CD)のプロモとして配布されたカセットテープ『1999 Reality Records Sampler』にも備わっていた。同作には『REQUIEM』をはじめ、「Reality」からニトロ名義の2作目としてリリースされる『BAMBU』、3作目の『Otogheebanasee』、そしてこのサンプラーテープとプロモの12インチにのみ『LIVE ‘99』が収録されており(このレコーディングでDELIがメンバーとして合流)、爆ぜる準備は徐々に整えられていく。そもそも“NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”という3つの単語が連なるグループ名になった背景はいかなるものだったのか。
「ラジコンが好きだったからニトログリセリンの“NITRO”、“MICROPHONE”は言わずもがなPAGERからで、“UNDERGROUND”は入れたい響きだよね、ってみんなで話してた。ローズ・オブ・ジ・アンダーグラウンドも好きだったしね。あとね、ニトロ部分に関しては、当時グラビアとかで超人気だった優香がメンバーだった4人組アイドルユニット NITROもいたから便乗しようとしてた気もする。8人の集合体をまとめて“ニトロ丼”って候補もあったくらいでさ、爆弾って意味合いも含めて。まあ、ネーミングに関してはおふざけが激しい感じでした」(MACKA-CHIN)
グループ名の命名に至った理由は、『Nitro Works』のリリースに合わせ販売を促進するため、それまでアートワークでキャッチコピー的に使っていた“NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”をグループ名にしたいという前川氏からの提案だったという。そして同年に前述した『BAMBU/LIVE ‘99』のプロモ12インチが宇田川町を中心に関係者へ配布され、いよいよニトロとしての活動基盤が整い始める(ちなみに『BAMBU』のメンバーはGORE-TEX/S-WORD/MACKA-CHIN/DABO、『LIVE ‘99』はDELI/SUIKEN/DABO/MACKA-CHIN/GORE-TEX/XBS/S-WORDとヴァース順のクレジット表記がされており、この時点でBIGZAMは未加入である)。
『LIVE ‘99』は予想を遙かに超える盛り上がりを見せた。DJ Viblam(DJ ヴィムラム)によるキャッチーなフックなど存在させぬ野郎感満載のトラック上で、メンバーがその時代に求められていたヒップホップの模範解答をマイクリレーで紡ぎ出す。NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDの名を知らしめるには十分すぎるクオリティを誇り、その存在に羨望の眼差しが向くようになった頃、間もなく時代は21世紀に突入しようとしていた。
記録的な数字を打ち出し舞台をメジャーへ
冒頭で「日本のヒップホップは長らく東京を中心に」と述べたが、その時代が指す“東京”と、ニトロが作り上げた“東京”は似ているようで異なる。誤解を恐れずに言ってしまえば、ニトロは東京を代表するアーティストとして名乗り出たいわけでもなく、シーンへの貢献もさして考えていない。原宿から渋谷(厳密に言えば原宿も渋谷区だが)、さらに宇田川町や円山町といった、極端に言ってしまえば活動範囲半径100メートル以内で行われている出来事を、ちょっとした悪ふざけと内輪ノリを楽曲に落とし込む。さらにはDJ WATARAI(DJ ワタライ)やDJ Viblam、Mr.Itagaki a.k.a. Ita-cho(ミスター イタガキ エーケーエー イタチョウ)、DJ HAZIMEらのプロデューサー勢、MUROやDEV LARGE(デヴラージ)といった全幅の信頼を置ける先輩ラッパー勢、レコ屋や服飾界隈で活躍するバイヤー勢、さらには映像分野で名を上げるクリエイター勢など、彼らの周辺には多分野から戦闘能力高めの手練が自然と集結する。音楽・ファッション・カルチャー、そして宇田川町という土地すら味方にした鉄壁の布陣は、結果としてそれまでになかった東京における最高峰のヒップホップの形を提示したのだ。そして21世紀の幕開けを飾り、彼らの代名詞的作品となるクラシック『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』が満を持して世に放たれる。
「ほかの曲は基本的にトラックがあって、そのときにラップをしたい人がラップするのがニトロのスタイルだったんですが、『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』は『メンバー8人全員でやってほしい』とレキシントンの会議室で伝えました。いま思い返すと、ちゃんとしたニトロのミーティングはこの1回だけかもしれません。『LIVE ‘99』は7人だったし、8人全員のマイクリレーをワタくん(DJ WATARAI)のトラックで作りたかったんですよね。ハヂメちゃん(DJ HAZIME)に作ってもらった『45 FINGERZ of DEATH』も同じ感じでみんなにお願いしました」(前川和昭)
マイクリレーの醍醐味を恐ろしいほどに凝縮した楽曲『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』は宇田川町を発信源とし、全国津々浦々へニトロの名を轟かせることになり、BIGZAMによる「渋谷宇田川発」というリリックは、後にも先にもNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDを象徴する言葉となった(なお、当時宇田川町のセレクトショップ『GROWAROUND(グロウアラウンド)』に勤務していたBIGZAMは、後にリリースされる同タイトルのアルバムに収録された『ASAMA 131』のレコーディングでニトロに正式加入している)。
機は熟した。グループの存在感を誇示し、シングルの爆発的ヒットを追い風にしたニトロはファーストアルバム『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』リリースの臨戦態勢に入る。前川氏は「Reality」から破格の2万枚販売の数字をメンバーに提案。「そんなに売れるわけないって」と反対したMACKA-CHINの不安をよそに、2000年10月上旬に全国流通されたCDは軒並み在庫切れとなり、入手できなかったリスナーも多かったはずだ。それもそのはず、「Reality」から販売された2万枚のCDは限定盤であり、メジャーレーベルである「Universal Music(ユニバーサルミュージック)」傘下に創設された「Def Jam Japan(デフジャム ジャパン)」からのメジャー流通が決定していたからだ(このニトロのメジャー流通アルバムが「Def Jam Japan」作品の1発目となる)。
現在は高額な機材や設備が整えられたスタジオの有無は無論、ある程度のノウハウを持ち合わせれば『TuneCore(チューンコア)』のようなプラットフォームから楽曲をリリース(配信)することができ、若い世代のラッパーはレーベル契約をそれほど重要視していない。しかし、前段でも述べたように、当時は十分なクオリティを担保するためにはレーベル契約が近道であり、セルアウトを非難する感覚とは反比例するかのごとく、メジャーと契約する気概は、今では考えられないほど強い傾向にあった。そういった背景から、「Def Jam Japan」とのメジャー契約は願ったり叶ったりのような形に見えるが、メンバーへの契約に関するアナウンスは事後報告だったとMACKA-CHINは吐露する。
「『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』のMVはDef Jam Japanに入ったから作れたってこともあるけど、Realityからリリースされたアルバムと、Def Jamから再販されたアルバムって内容が違うじゃない? 正直、気持ちのいいことではなかったよね。でもさ、Def Jamから再発されたことで『blast(ブラスト)』みたいな専門誌から『WOOFIN’(ウーフィン)』とか『WARP(ワープ)』『Fine(ファイン)』とかのストリートファッション誌でも大きく特集してもらって、ヒップホップだけじゃないジャンルの人たちにも知ってもらえたと思う。そういうありがたさはすごくあったけど、めちゃくちゃ売れてるのに僕らに見返りは何もなかったのよ。だから自分たちで会社作ったほうがいいよね、ってことで有限会社ナイトリッチを立ち上げたんだ」(MACKA-CHIN)
結果的にメジャー流通に乗ったリパッケージ・アルバムは、(Reality盤も含め)15万枚以上の売り上げを記録。同「Def Jam Japan」からDABOとS-WORD、SUIKENは「Sony Music(ソニーミュージック)」、MACKA-CHINは「Victor(ビクター)」と、ニトロのメンバーは各々ソロ活動の舞台もメジャーへと移行する好結果を生む。そして、ビジネスの才覚を持ち合わせたメンバーによって、音楽制作やマネジメントを主とする有限会社ナイトリッチが設立され、のちにアパレルブランド〈NITROW(ナイトロウ)〉も立ち上がり、ニトロの活動はグループとソロ、そしてファッションも包括した多角的展開へとフェイズを移す準備が整えられる。
Vol.2ではメンバーのソロ活動を振り返りながら、XBSのソロインタビューと共にアパレル事業を回顧するVol.3を公開していく。
in HTML format, including tags, to make it appealing and easy to read for Japanese-speaking readers aged 20 to 40 interested in fashion. Organize the content with appropriate headings and subheadings (h1, h2, h3, h4, h5, h6), translating all text, including headings, into Japanese. Retain any existing
tags from
日本のヒップホップは、黎明期から長らく東京を中心に歴史を築き上げてきた。ブラックミュージックに傾倒し、ラップというアートフォームに憧れを抱いた若者は、未知のジャンルへの可能性と、体感したことのない洗練されたスタイルに胸を高鳴らせる。1990年代中期、『DA.YO.NE』や『今夜はブキー・バック』が巷を席巻した第一次ラップブームが訪れた時代 ── テレビや新聞、情報誌などのマスメディアが伝聞する情報に世の中は沸き立ち、「ヒップホップ」というワードが持てはやされる時代が到来した。しかし一方では、水面下で巻き起こる「何がリアルで何がフェイクか」論争が顕在化し、「これが本当にヒップホップなのか」と疑念を抱く者も現れ、この時代から自らのセンスでリアルをジャッジする審美眼と、セルアウト(商業主義)を忌み嫌う文化は並行して走り続ける。そんなことはお構いなしにオーバーグラウンドでは「チェケラッチョ」という言葉がミーム化し、ラップが常態化していく状況とは裏腹に、アンダーグラウンドではそんな言葉を用いることなく、日々スキルを磨く面々が切磋琢磨していた。
それからほどなくして、渋谷のクラブ『CAVE』では、セルアウトの動向など見向きもせぬ面々が新たなイベント「A BAOA QU」を始動させ、徐々に耳目を集めるパーティとなっていた。大袈裟に表現するまでもなく、そこに集う顔ぶれは、「誰よりも自分が一番イケている」精神を宿す音楽/クラブ/ファッション業界に従事する面々、そしてDJ、ダンサー、ラッパーたちだ。その時代「現場」と呼ばれるクラブという空間は、自らのセンスを自負する者たちが同じテンションで邁進できる仲間を無自覚ながら探す場所としても機能していた。SNSはおろか、インターネットすらままならない時代において、うまい具合にフィールする人間を探し出すことは容易なことでないが、その空間でのちに誕生するNITRO MICROPHONE UNDERGROUND(ニトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンド)の原形が形成されることになる──。本稿ではメンバーや関係者の言葉を引用しながら、ニトロ結成前から活動休止、そして再始動から現在に至るまでの四半世紀における歴史を振り返っていく。MACKA-CHIN(マッカチン)の回想から始めよう。
「ニトロはキングギドラや雷、RHYMESTER(ライムスター)みたいに『グループを結成して曲を作って、アンダーグラウンドでライブ活動!』とか考えてスタートしたわけじゃないんですよ。ニトロ結成前のつながりで言えば、僕は当時原宿で働いてたんだけど、GORE-TEX(ゴアテックス)とS-WORD(スウォード)が渋谷で働いてて、XBS(エックスビーエス)とは高校で同級生。SUIKEN(スイケン)とDABO(ダボ)はDJ HAZIME(DJ ハジメ)やK-BOMB(ケーボン)とチームを組んで西麻布でイベントをやっていたのね。みんながそれぞれヒップホップが好きで、知り合いが働いてる店やクラブを回ることで自然と交流を深めていたんだと思う。そのぐらいのタイミングになるのかな、先輩から『CAVEでなんかイベントやれよ』って誘われて。月イチ第一水曜日のイベントだったんだけど、回を重ねるごとに人がパンパンになってきてね。ただ、この時点でDELI(デリ)とBIGZAM(ビグザム)とはまだ合流はしていなかったかな」(MACKA-CHIN)
今では到底考えられないが、トラックを制作できる機材はもちろん、レーベルと契約しなければレコーディング環境すら整えるのが困難な時代。そのため当時のライブは、海外アーティストの12インチに収録されたインストをオケに自作のラップを乗せるスタイルが主流で、その「オケを何にするか(しているか)」で、センスが見極められた時代と言っても過言ではない。そんなイベントの活況を耳にした『Manhattan Records(マンハッタン・レコード)』や『CISCO(シスコ)』といった宇田川町の代名詞でもあるレコードショップのスタッフも、イベントに足を運ぶようになる。あらゆるカルチャーの坩堝となった空間で、イベントを盛り上げる30人前後のメンバーは“約 NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”として自然と結束を固めていく。その好機を見逃さなかったのが、「一緒に曲を作らないか?」とMACKA-CHINに声をかけた元『Manhattan Records』、後にニトロのソロ/グループ作品をリリースする「Reality Records(リアリティ・レコーズ)」のエグゼクティブ・プロデューサー/A&Rを務める「株式会社レキシントン」の前川和昭氏だ。しかし、セルアウト拒絶反応時代も相まってか、約ニトロのメンバーの中には「デビューとかマジどうでもいい」と見向きもしない勢すら存在したという。そして、活況や好機とは裏腹に「まっとうに働くべき年齢」という壁に直面し、強固となった結束を就職のためにほどかざるを得ない世代も現れ、結果的に残ったメンバーがニトロの原形を担うことになる。
「渋谷宇田川発」というリアリティ
1990年代、海外ではWu-Tang Clan(ウータン・クラン)やBoot Camp Clik(ブート・キャンプ・クリック)、D.I.T.C.(ディーアイティーシー)など、日本でもLAMP EYE『証言』に象徴されるように、大所帯で回していくマイクリレーには言葉で説明しきれないほどのエネルギーが感じ取られた。それらに倣うように、「A BAOA QU」に出演していたMACKA-CHIN、S-WORD、GORE-TEX、SUIKENによる4人のマイクリレー『REQUIEM』(99年発売。プロデュースはDJ WATARAI)が「Reality Records」からリリースされるまで、それほど時間は要さなかった。前述した前川氏が当時を振り返る。
「マンハッタンで働き始めた94年当時は、US/UK直送のヒップホップ/R&Bを中心に扱っていたんですが、僕がMICROPHONE PAGER(マイクロフォン・ペイジャー)や雷が大好きだったこともあり、日本語ラップも積極的に取り扱うようになっていきました。並行して96年頃からBEN THE ACE(ベン ザ エース)さんのレーベル SPELLBOUND(スペルバウンド)や、MURO(ムロ)さんのレーベル INCREDIBLE(インクレディブル)で裏方をされていた先輩の手伝いもしていたんですが、マンハッタンでもレーベル事業をやりたい気運が高まっていた98年、創業者である平川(雅夫)さんから『スタジオを作るからレーベル始めないか?』と言われたのがReality Recordsの始まりです。
その頃ヨシテル(MACKA-CHIN)が原宿のレコ屋で働いていたんですけど、昼間会いに行ってメシを食いながらいろいろ話したのを覚えています。そこで『トラ(GORE-TEX)のレコーディングの合間に録ったデモがあるから、それを出さない?』と言われた曲が、後にRealityからリリースする『REQUIEM』。設立当時の方針は『自分が好きなアーティストをリリースする』という、至ってシンプルなものでした」(前川和昭)
前述した通り、まだニトロの原形であった理由から『REQUIEM』のクレジットは「S-WORD/MACKA-CHIN/GORE-TEX」となっている(客演としてSUIKENも参加しているがクレジットは未表記)。前川氏が述べたように、レーベル事業のみならず、日本語ラップそのものの機運が高まっていた時代でもあり、同時に『REQUIEM』の12インチが8000枚即完という結果は、日本語ラップの機運という枠をすら越えて、宇田川町がカルチャーの発信源となるきっかけも作り出した。
当時の宇田川町の雰囲気を体感した者なら、良い意味でも悪い意味でも記憶から消えることのない濃すぎる思い出があるだろう。例えば、宇田川町に所狭しとひしめき合うレコードショップや洋服屋のスタッフはいつも横柄で、サービス業の風上にも置けたものじゃない。店内では客をないがしろにするスタッフが悪ノリ内輪ノリで盛り上がっている。だが、必死で最先端の情報を求める若者にとっては、その状況すらある種有益な障壁であり、誰よりも早くイケてるアナログや洋服を手にしかたかったはずだ。とはいえ、思い返してみても、勤務するショップスタッフの知識やセンスに疑う余地はなく、その威圧的かつ塩対応だったからこそ、誰もが貪欲になれた恩恵もある。ニトロは、その感覚をもっとも体現・具現化した宇田川発(初)のヒップホップグループだったとすら思う。
これはレコードショップに限った話だが、誰よりも早く入手すべく、その物欲を高める要素に「Promotional Use Only, Not For Sale」という文字列がある。「インストはプロモにしか収録されていない」「リミックスはプロモにだけ収録されている」「この12インチはプロモでしか存在しない」 ── この文字列の恐ろしいほどの引力は、『REQUIEM』リリースからほどなくして、初のNITRO MICROPHONE UNDERGROUND名義として販売された『Nitro Works』(CD)のプロモとして配布されたカセットテープ『1999 Reality Records Sampler』にも備わっていた。同作には『REQUIEM』をはじめ、「Reality」からニトロ名義の2作目としてリリースされる『BAMBU』、3作目の『Otogheebanasee』、そしてこのサンプラーテープとプロモの12インチにのみ『LIVE ‘99』が収録されており(このレコーディングでDELIがメンバーとして合流)、爆ぜる準備は徐々に整えられていく。そもそも“NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”という3つの単語が連なるグループ名になった背景はいかなるものだったのか。
「ラジコンが好きだったからニトログリセリンの“NITRO”、“MICROPHONE”は言わずもがなPAGERからで、“UNDERGROUND”は入れたい響きだよね、ってみんなで話してた。ローズ・オブ・ジ・アンダーグラウンドも好きだったしね。あとね、ニトロ部分に関しては、当時グラビアとかで超人気だった優香がメンバーだった4人組アイドルユニット NITROもいたから便乗しようとしてた気もする。8人の集合体をまとめて“ニトロ丼”って候補もあったくらいでさ、爆弾って意味合いも含めて。まあ、ネーミングに関してはおふざけが激しい感じでした」(MACKA-CHIN)
グループ名の命名に至った理由は、『Nitro Works』のリリースに合わせ販売を促進するため、それまでアートワークでキャッチコピー的に使っていた“NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”をグループ名にしたいという前川氏からの提案だったという。そして同年に前述した『BAMBU/LIVE ‘99』のプロモ12インチが宇田川町を中心に関係者へ配布され、いよいよニトロとしての活動基盤が整い始める(ちなみに『BAMBU』のメンバーはGORE-TEX/S-WORD/MACKA-CHIN/DABO、『LIVE ‘99』はDELI/SUIKEN/DABO/MACKA-CHIN/GORE-TEX/XBS/S-WORDとヴァース順のクレジット表記がされており、この時点でBIGZAMは未加入である)。
『LIVE ‘99』は予想を遙かに超える盛り上がりを見せた。DJ Viblam(DJ ヴィムラム)によるキャッチーなフックなど存在させぬ野郎感満載のトラック上で、メンバーがその時代に求められていたヒップホップの模範解答をマイクリレーで紡ぎ出す。NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDの名を知らしめるには十分すぎるクオリティを誇り、その存在に羨望の眼差しが向くようになった頃、間もなく時代は21世紀に突入しようとしていた。
記録的な数字を打ち出し舞台をメジャーへ
冒頭で「日本のヒップホップは長らく東京を中心に」と述べたが、その時代が指す“東京”と、ニトロが作り上げた“東京”は似ているようで異なる。誤解を恐れずに言ってしまえば、ニトロは東京を代表するアーティストとして名乗り出たいわけでもなく、シーンへの貢献もさして考えていない。原宿から渋谷(厳密に言えば原宿も渋谷区だが)、さらに宇田川町や円山町といった、極端に言ってしまえば活動範囲半径100メートル以内で行われている出来事を、ちょっとした悪ふざけと内輪ノリを楽曲に落とし込む。さらにはDJ WATARAI(DJ ワタライ)やDJ Viblam、Mr.Itagaki a.k.a. Ita-cho(ミスター イタガキ エーケーエー イタチョウ)、DJ HAZIMEらのプロデューサー勢、MUROやDEV LARGE(デヴラージ)といった全幅の信頼を置ける先輩ラッパー勢、レコ屋や服飾界隈で活躍するバイヤー勢、さらには映像分野で名を上げるクリエイター勢など、彼らの周辺には多分野から戦闘能力高めの手練が自然と集結する。音楽・ファッション・カルチャー、そして宇田川町という土地すら味方にした鉄壁の布陣は、結果としてそれまでになかった東京における最高峰のヒップホップの形を提示したのだ。そして21世紀の幕開けを飾り、彼らの代名詞的作品となるクラシック『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』が満を持して世に放たれる。
「ほかの曲は基本的にトラックがあって、そのときにラップをしたい人がラップするのがニトロのスタイルだったんですが、『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』は『メンバー8人全員でやってほしい』とレキシントンの会議室で伝えました。いま思い返すと、ちゃんとしたニトロのミーティングはこの1回だけかもしれません。『LIVE ‘99』は7人だったし、8人全員のマイクリレーをワタくん(DJ WATARAI)のトラックで作りたかったんですよね。ハヂメちゃん(DJ HAZIME)に作ってもらった『45 FINGERZ of DEATH』も同じ感じでみんなにお願いしました」(前川和昭)
マイクリレーの醍醐味を恐ろしいほどに凝縮した楽曲『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』は宇田川町を発信源とし、全国津々浦々へニトロの名を轟かせることになり、BIGZAMによる「渋谷宇田川発」というリリックは、後にも先にもNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDを象徴する言葉となった(なお、当時宇田川町のセレクトショップ『GROWAROUND(グロウアラウンド)』に勤務していたBIGZAMは、後にリリースされる同タイトルのアルバムに収録された『ASAMA 131』のレコーディングでニトロに正式加入している)。
機は熟した。グループの存在感を誇示し、シングルの爆発的ヒットを追い風にしたニトロはファーストアルバム『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』リリースの臨戦態勢に入る。前川氏は「Reality」から破格の2万枚販売の数字をメンバーに提案。「そんなに売れるわけないって」と反対したMACKA-CHINの不安をよそに、2000年10月上旬に全国流通されたCDは軒並み在庫切れとなり、入手できなかったリスナーも多かったはずだ。それもそのはず、「Reality」から販売された2万枚のCDは限定盤であり、メジャーレーベルである「Universal Music(ユニバーサルミュージック)」傘下に創設された「Def Jam Japan(デフジャム ジャパン)」からのメジャー流通が決定していたからだ(このニトロのメジャー流通アルバムが「Def Jam Japan」作品の1発目となる)。
現在は高額な機材や設備が整えられたスタジオの有無は無論、ある程度のノウハウを持ち合わせれば『TuneCore(チューンコア)』のようなプラットフォームから楽曲をリリース(配信)することができ、若い世代のラッパーはレーベル契約をそれほど重要視していない。しかし、前段でも述べたように、当時は十分なクオリティを担保するためにはレーベル契約が近道であり、セルアウトを非難する感覚とは反比例するかのごとく、メジャーと契約する気概は、今では考えられないほど強い傾向にあった。そういった背景から、「Def Jam Japan」とのメジャー契約は願ったり叶ったりのような形に見えるが、メンバーへの契約に関するアナウンスは事後報告だったとMACKA-CHINは吐露する。
「『NITRO MICROPHONE UNDERGROUND』のMVはDef Jam Japanに入ったから作れたってこともあるけど、Realityからリリースされたアルバムと、Def Jamから再販されたアルバムって内容が違うじゃない? 正直、気持ちのいいことではなかったよね。でもさ、Def Jamから再発されたことで『blast(ブラスト)』みたいな専門誌から『WOOFIN’(ウーフィン)』とか『WARP(ワープ)』『Fine(ファイン)』とかのストリートファッション誌でも大きく特集してもらって、ヒップホップだけじゃないジャンルの人たちにも知ってもらえたと思う。そういうありがたさはすごくあったけど、めちゃくちゃ売れてるのに僕らに見返りは何もなかったのよ。だから自分たちで会社作ったほうがいいよね、ってことで有限会社ナイトリッチを立ち上げたんだ」(MACKA-CHIN)
結果的にメジャー流通に乗ったリパッケージ・アルバムは、(Reality盤も含め)15万枚以上の売り上げを記録。同「Def Jam Japan」からDABOとS-WORD、SUIKENは「Sony Music(ソニーミュージック)」、MACKA-CHINは「Victor(ビクター)」と、ニトロのメンバーは各々ソロ活動の舞台もメジャーへと移行する好結果を生む。そして、ビジネスの才覚を持ち合わせたメンバーによって、音楽制作やマネジメントを主とする有限会社ナイトリッチが設立され、のちにアパレルブランド〈NITROW(ナイトロウ)〉も立ち上がり、ニトロの活動はグループとソロ、そしてファッションも包括した多角的展開へとフェイズを移す準備が整えられる。
Vol.2ではメンバーのソロ活動を振り返りながら、XBSのソロインタビューと共にアパレル事業を回顧するVol.3を公開していく。
and integrate them seamlessly into the new content without adding new tags. Ensure the new content is fashion-related, written entirely in Japanese, and approximately 1500 words. Conclude with a “結論” section and a well-formatted “よくある質問” section. Avoid including an introduction or a note explaining the process.